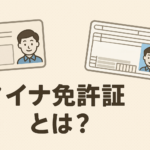「ちょっとくらいなら大丈夫だろう」
「赤信号で止まっている間なら…」
運転中にスマートフォンが気になり、つい手を伸ばしてしまった経験はありませんか?しかし、その「ちょっと」が、取り返しのつかない大事故につながる危険性をはらんでいます。そして、その「ちょっと」が、厳しい罰則の対象となることをご存知でしょうか。
スマートフォンの急速な普及に伴い、「ながら運転」による悲惨な交通事故が後を絶ちません。この事態を重く受け止め、2019年12月1日に道路交通法が改正され、スマートフォンの「ながら運転」に対する罰則が大幅に強化されました。
この記事では、運転免許を取得したばかりの初心者の方や、久しぶりにハンドルを握るペーパードライバーの方にも分かりやすく、「ながら運転」の定義から強化された罰則の内容、そして、どうすれば「ながら運転」を防げるのか、具体的な対策まで詳しく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「ながら運転」の本当の怖さと、安全運転のために何をすべきかが明確になっているはずです。あなた自身と、あなたの大切な人の命を守るために、ぜひ最後までお付き合いください。
そもそも「ながら運転」とは?どこからが違反になるのか
「ながら運転」と一括りに言っても、具体的にどのような行為が違反となるのか、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。まずは、法律で定められている違反行為の基本から確認していきましょう。
道路交通法では、スマートフォンの「ながら運転」に関する違反を大きく2つのケースに分けて規定しています。
違反ケース1:スマートフォンの画面を注視する「保持」
一つ目は、運転中にスマートフォンなどを手で持って(保持して)、その画面をじっと見つめる(注視する)行為です。これは「携帯電話使用等(保持)」と呼ばれます。
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 手に持って通話する
- 手に持ってメールやLINEのメッセージを確認する、または作成・送信する
- 手に持ってインターネットのウェブサイトを見る
- 手に持って地図アプリの画面をじっと見る
- 手に持ってゲームをする
ポイントは「手に持っていること」と「画面を注視していること」です。たとえ通話をしていなくても、手に持って画面を見ているだけで違反となります。「注視」の定義は明確に「何秒以上」と決まっているわけではありませんが、一般的には2秒以上画面を見続けると注視と判断されることが多いようです。
つまり、「赤信号で停車中にちょっとLINEの返信を…」という行為も、完全に車が停止している状態(例えば、エンジンを切っている状態など)でなければ、違反とみなされる可能性が非常に高いのです。
違反ケース2:交通の危険を生じさせる「交通の危険」
二つ目は、スマートフォンの使用によって、実際に交通の危険を生じさせた場合です。これは「携帯電話使用等(交通の危険)」と呼ばれ、一つ目の「保持」よりもさらに重い罰則が科せられます。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- スマートフォンに気を取られて、前の車に追突してしまった
- 画面を見ていて、歩行者や自転車に気づくのが遅れ、事故を起こしてしまった
- 通話に夢中になり、ハンドル操作を誤って蛇行運転をしてしまった
- カーナビアプリを操作していて、信号を見落として交差点に進入してしまった
こちらは、スマートフォンの使用が直接的な原因となって事故や危険な状況を引き起こした場合に適用されます。たとえ物損事故であっても、スマートフォンを操作していたことが原因であれば、この「交通の危険」に問われることになります。
【知らないと怖い】大幅に強化された罰則の全貌
2019年12月の法改正で、「ながら運転」の罰則は以前とは比べ物にならないほど厳しくなりました。軽い気持ちで行った行為が、あなたの運転免許や経済状況に大きな打撃を与える可能性があります。
ここでは、具体的にどのように罰則が強化されたのかを詳しく見ていきましょう。
違反点数と反則金
まずは、違反点数と反칙金です。これは、先ほど解説した2つの違反ケースによって大きく異なります。
スマートフォンの画面を注視する「保持」の場合
| 改正後(現在) | 改正前 | |
| 違反点数 | 3点 | 1点 |
| 反則金(普通車) | 18,000円 | 6,000円 |
改正前と比較して、違反点数も反則金も3倍に引き上げられました。違反点数3点というのは、例えば速度超過(一般道で15km/h以上20km/h未満)と同じ点数です。決して軽い違反ではないことがお分かりいただけるでしょう。
免許を取得して1年以内の初心者ドライバーの場合、合計で3点以上の違反をすると「初心者運転者講習」の対象となります。つまり、「ながら運転」を一度でも摘発されると、この講習を受けなければならなくなるのです。
交通の危険を生じさせた場合
| 改正後(現在) | 改正前 | |
| 違反点数 | 6点 | 2点 |
| 反則金 | 適用なし(刑事罰の対象) | 9,000円(普通車) |
こちらはさらに厳しくなっています。違反点数は一気に6点。これは、免許停止処分(前歴がない場合で30日間)の対象となる点数です。つまり、事故を起こした場合は一発で免許停止になってしまうのです。
さらに重要なのが、反則金の適用がなくなったことです。これは、青切符(交通反則通告制度)で処理される比較的軽微な違反ではなく、赤切符が切られ、刑事手続きに移行することを意味します。
刑事罰(懲役または罰金)
「交通の危険」を生じさせた場合は、刑事罰の対象となり、懲役または罰金が科せられます。
- 懲役または罰金:「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
改正前は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」でしたから、こちらも大幅に厳罰化されていることが分かります。単なる交通違反ではなく、犯罪として扱われるということを、肝に銘じておく必要があります。
なぜ「ながら運転」はこれほど危険なのか?
なぜ、これほどまでに罰則が強化されたのでしょうか。それは、スマートフォンの「ながら運転」が、私たちの想像をはるかに超える危険な行為だからです。
脳は2つのことを同時に処理できない
「自分は運転に慣れているから、少しスマホを見るくらい大丈夫」
そう考える人もいるかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。人間の脳は、複数の情報を同時に、かつ完璧に処理するようにできていません。
運転中は、前方車両の動き、信号の色、標識、歩行者や自転車の有無、道路の状況など、膨大な情報を瞬時に処理し、判断を下す必要があります。そこにスマートフォンの画面という別の情報が入ってくると、脳の処理能力はパンクしてしまいます。
結果として、危険の発見が遅れたり、判断を誤ったりする確率が格段に高まるのです。
わずか2秒が命取りに。車は思った以上に進んでいる
時速60kmで走行している車は、わずか1秒で約17メートルも進みます。もし、あなたがスマートフォンの画面に2秒間目を落としたとしたら、その間に車は約34メートルも進んでいる計算になります。
34メートルといえば、25メートルプールよりも長い距離です。その間、あなたは前方から完全に目を離している状態、つまり「目隠し運転」をしているのと同じことなのです。もしその先に、急ブレーキをかけた車や、道路に飛び出してきた子供がいたら…?想像するだけで恐ろしくなります。
ある調査によれば、スマートフォンを操作しながら運転した場合の反応時間は、飲酒運転時よりも遅れるというデータもあります。「ながら運転」は、飲酒運転と同じくらい、あるいはそれ以上に危険な行為であると認識してください。
これで安心!「ながら運転」を防ぐための具体的な方法
では、どうすれば誘惑に打ち勝ち、「ながら運転」を防ぐことができるのでしょうか。精神論だけではなかなか難しいものです。ここでは、誰でも今日から実践できる具体的な対策を5つご紹介します。
1. 運転前に「ドライブモード」や「機内モード」に設定する
スマートフォンには、運転中の通知を制限する機能が備わっています。
- iPhoneの場合:「運転集中モード」
- Androidの場合:「ドライブモード」
これらのモードを設定しておけば、運転中は電話の着信やアプリの通知が来なくなり、画面も表示されなくなります。これなら、通知音が気になってスマホに手を伸ばす、という状況を防ぐことができます。
また、もっとシンプルに「機内モード」に設定してしまうのも効果的です。これなら通信自体を遮断できるため、誘惑の元を断つことができます。
2. スマートフォンはカバンや手の届かない場所に置く
物理的にスマートフォンに触れられない環境を作るのも、非常に有効な対策です。
- 助手席や後部座席に置いたカバンの中に入れる
- グローブボックスにしまっておく
- 同乗者に預かってもらう
運転席から手の届かない場所に置いてしまえば、触りたくても触れません。特に、運転に慣れていない初心者の方や、ついついスマホを触ってしまう癖がある方は、この方法を徹底することをおすすめします。
3. 地図アプリは音声案内を活用し、画面を注視しない
最近では、カーナビ代わりにスマートフォンの地図アプリを利用する方も多いでしょう。地図アプリの利用自体が違反というわけではありませんが、問題となるのはその使い方です。
運転中に画面を注視したり、手で持って操作したりするのは違反です。地図アプリを使う際は、以下の点を必ず守りましょう。
- 出発前に目的地を設定し、ルート案内を開始しておく
- スマートフォンは、視界を妨げない場所に車載ホルダーでしっかりと固定する
- 運転中は音声案内をメインに利用し、画面をじっと見続けない
- もしルート変更などの操作が必要になった場合は、必ず安全な場所に停車してから行う
車載ホルダーは、エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプや、ダッシュボードに設置するタイプなど様々なものがあります。自分の車に合った、安定感のあるものを選びましょう。
4. ハンズフリー装置を使えば通話はOK?注意点を理解する
「ハンズフリーなら通話してもいいんでしょ?」と考える方もいるかもしれません。確かに、道路交通法上、ハンズフリー装置(イヤホンマイクや、カーオーディオのBluetooth機能など)を使用しての通話は、直ちに「保持」違反にはなりません。
しかし、だからといって安全というわけではありません。
重要なのは、通話の内容に集中するあまり、運転への注意力が散漫になってしまうことです。難しい話や、感情的になるような話をしていると、どうしても運転がおろそかになりがちです。その結果、危険の発見が遅れたり、操作を誤ったりして「交通の危険」に問われる可能性は十分にあります。
また、多くの自治体では、条例によってハンズフリーイヤホンの使用を禁止または制限している場合があります。例えば、イヤホンによって周囲の音(緊急車両のサイレン、踏切の警報音など)が聞こえにくくなることが危険と判断されるためです。
ハンズフリー装置を使う場合は、あくまでも緊急時やごく短い連絡のみに留め、長電話は絶対にやめましょう。そして、お住まいの地域の条例も一度確認しておくことをお勧めします。
5. どうしても必要な場合は、必ず安全な場所に停車する
仕事の連絡、家族からの緊急の電話など、どうしても運転中に対応しなければならない場面もあるかもしれません。
その場合は、絶対に焦って運転中に操作をしないでください。
必ず、コンビニの駐車場やサービスエリア、パーキングなど、他の交通の妨げにならない安全な場所に車を完全に停車させてから、スマートフォンを操作するようにしましょう。そのわずかな手間を惜しんだことが、一生の後悔につながる可能性があるのです。
まとめ:あなたの運転は、多くの人の命と隣り合わせ
今回は、スマートフォンの「ながら運転」について、違反の定義から厳罰化された内容、そして具体的な対策までを詳しく解説しました。
- 運転中にスマホを手に持って画面を見るだけで違反(違反点数3点、反則金18,000円)
- ながら運転で事故を起こすと一発で免許停止、さらに刑事罰の対象に
- わずか2秒のよそ見が、重大事故につながる
- 対策は、運転前にスマホを触れない環境を作ることが最も効果的
法改正による罰則強化は、単にドライバーを罰するためだけのものではありません。それは、「ながら運転は、あなたと周りの人の命を奪いかねない、極めて危険な行為である」という社会からの強いメッセージです。
運転席に座り、ハンドルを握るということは、多くの人の命を預かるということです。その責任を自覚し、「運転中はスマートフォンを触らない」という当たり前のルールを徹底すること。それが、安全なカーライフを送るための、そして悲しい事故をなくすための、最も重要で基本的な第一歩なのです。
この記事が、あなたの安全運転への意識を新たにするきっかけとなれば幸いです。