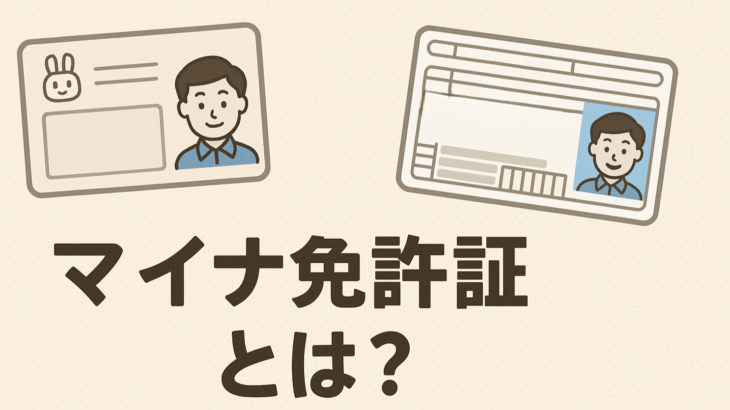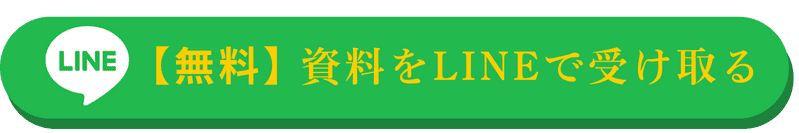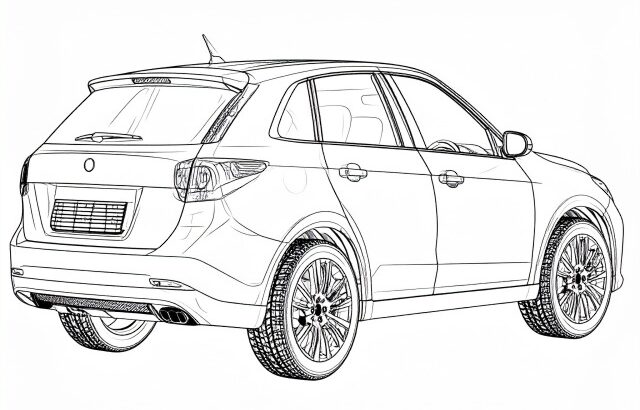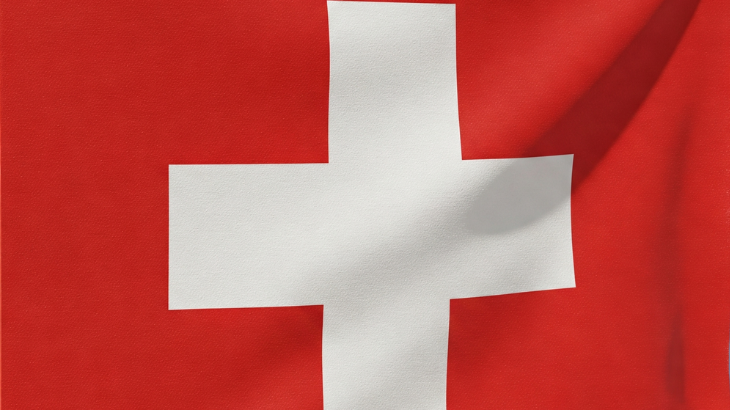マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報を記録し、従来の運転免許証の代わりとして利用できるようになる仕組みが「マイナ免許証」です。2025年3月24日から開始され、引き続き従来の運転免許証も利用可能なため、運転免許証を保有している方は「マイナ免許証のみ」「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」「運転免許証のみ」の3つのいずれかを選んで所持できます。ここでは、マイナ免許証の概要やメリット・注意点、手続の進め方などを分かりやすく解説します。
マイナ免許証の概要
導入の背景
日本では人口減少や少子高齢化に伴って、行政サービスの維持が難しくなると懸念されています。そこで、行政手続や各種サービスの効率化を推進すべく、マイナンバーカードを活用したデジタル化が進められてきました。運転免許証の分野でも、デジタル技術を使った利便性向上が求められてきた結果、2025年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)の運用が開始されることになりました。
利用開始日と選択肢
2025年3月24日以降に免許取得・更新などの手続を行う際、以下の3パターンから運転免許証の持ち方を選べます。
- マイナ免許証のみ
- 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち
- 運転免許証のみ
どれを選んでも運転自体は可能ですが、住所変更のワンストップ化やオンライン講習の利用など、メリットが受けられる条件が異なるため、ライフスタイルに合った選び方を検討する必要があります。
マイナンバーカードへの記録情報
マイナ免許証はマイナンバーカードのICチップ内に免許情報が記録されます。マイナンバーカードの表面には運転免許に関する情報(免許の種類や有効期限など)は記載されず、券面上はこれまでと同じマイナンバーカードに見えます。ICチップに記録される情報は下記のとおりです。
- マイナ免許証の番号
- 運転免許取得日・マイナ免許証の有効期間の末日
- 運転免許の種類(普通・大型・二輪など)
- 免許条件(AT限定・眼鏡・補聴器など)
- 顔写真
- 色区分(ゴールド、若草色、薄青色など)
マイナ免許証のメリットと注意点
メリット1:更新時のオンライン講習
マイナ免許証を保有している優良運転者や一般運転者の方は、免許の更新講習をオンラインで受講できるようになります。これまでは運転免許センターや警察署などで対面講習を受ける必要がありましたが、オンライン講習によって好きな場所・時間帯に受講できるため、更新当日の待ち時間が大幅に短縮される点が大きなメリットです。
ただし、このオンライン講習を受けるためには、あらかじめ運転免許センターなどでマイナンバーカードの署名用電子証明書(英数字6〜16桁の暗証番号)を提出し、マイナポータルとの連携手続を行う必要があります。講習後には結局、視力検査や写真撮影などのために運転免許センター等に行く必要はありますが、講習そのものを好きな時間に受けられるのは大きな利点でしょう。
メリット2:住所変更手続きのワンストップ化
「マイナ免許証のみ」を持つ方は、住所や氏名などの変更があった場合、市区町村役場での手続だけで完了します。従来は市区町村役場と運転免許センターなどに別々に行って届け出る必要がありましたが、マイナ免許証のみの方は警察への届け出が不要になります。これにより、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わったときの手間が大幅に減るでしょう。
なお、このワンストップサービスを使うには、運転免許センターなどで署名用電子証明書と免許情報を紐付ける手続を先に行う必要があるため、利用前に所定の手続を済ませておきましょう。また、「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」や「運転免許証のみ」の方は、引き続き運転免許センター等での住所変更手続が求められます。
メリット3:手数料の安さ
マイナ免許証を「のみ」で保有する場合、運転免許の新規取得や更新の際に必要となる手数料が最も安くなります。大まかな比較は以下のとおりです(具体的金額は都道府県や状況によって変わる可能性がありますが、基本的には国が示す統一的な金額で運用される見通しです)。
- マイナ免許証のみ:新規取得1,550円、更新2,100円
- 運転免許証のみ:新規取得2,350円、更新2,850円
- 2枚持ち:新規取得2,450円、更新2,950円
このように、マイナ免許証のみを選べば、発行コストを抑えられます。一方、2枚持ちや従来の運転免許証だけを維持する場合は、やや割高にはなりますが、免許証を使ったサービスを従来と変わらず利用できる安心感があるという見方もできます。
メリット4:経由地更新の迅速化と申請期間の延長
マイナ免許証(のみ、または2枚持ち)を選んだ優良・一般運転者は、住所地以外の都道府県警(運転免許センターや警察署など)で行う経由地更新がよりスムーズになります。特に「マイナ免許証のみ」の更新であれば、その日のうちに更新手続が完了するため、出張などで居住地を長期間離れている人にとっては非常に有用です。また、更新申請期間も「更新期間初日から免許証等の有効期間の末日まで」に延長されるため、余裕をもって手続が行えます。
メリット5:カードが1枚で済む
日頃からマイナンバーカードを携帯している人にとっては、マイナ免許証に一本化することで、運転の際に別途運転免許証を持ち歩く必要がなくなります。つまり、財布やカードケースがかさばるのを防げる点も便利です。
注意点1:マイナ免許証への対応が整っていないサービス
従来のプラスチックカード型の免許証番号を確認することを前提としている一部のレンタカー・カーシェア業者などでは、サービス開始当初、マイナ免許証が利用できないケースが出てきています。これは、マイナ免許証を読み取る環境(ICカードリーダーやアプリなど)が整備されておらず、従来の目視確認に依存していたフローに対応できていないためです。今後、段階的に対応が進む可能性は高いものの、当面は「マイナ免許証のみだと利用不可」としているサービスもあるため、よく利用する企業や業者の対応状況を確認してから2枚持ちを検討するのも良いでしょう。
注意点2:国外運転免許証申請時の留意
海外で運転する予定がある方は要注意です。国外運転免許証を申請するときに、マイナ免許証のみを持っていると渡航先の国によっては従来の免許証が必要になる場合があります。海外渡航中に車を運転することがある方は、運転免許証を引き続き持っておくか、必要に応じて2枚持ちへ切り替えることを検討しましょう。
注意点3:マイナンバーカードの更新とマイナ免許証の有効期限
マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限は異なります。特にマイナンバーカードを更新すると、新しいカードのICチップには免許情報が記録されていないため、改めて免許情報の記録を行わなければ運転することができません。マイナンバーカードの有効期限が近い場合は、先にマイナンバーカードを更新してからマイナ免許証手続をするか、あるいは従来の運転免許証との2枚持ちにしておくと手間を減らせます。
運転免許証の持ち方の選択肢
免許証をどのように持つかは以下の3つの選択肢があります。自分のライフスタイルや利用状況に応じてベストな選択をしましょう。
1. マイナ免許証のみ
マイナンバーカードのICチップに免許情報を記録し、現在所持している運転免許証を返納する方法です。カードが1枚になるうえに発行手数料が安く、オンライン講習や住所変更ワンストップサービスなどのメリットを最大限に享受できます。その反面、マイナ免許証に未対応のサービスがある場合は利用できなかったり、海外渡航時に不便が生じる可能性がある点は要注意です。また、マイナンバーカードの更新時には再度免許情報の記録が必要になります。
2. 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち
マイナンバーカードを運転免許証としても使えるようにしつつ、従来の運転免許証も手元に残しておく方法です。サービスごとに従来の免許証を提示したり、マイナ免許証を使ってオンライン講習を受けたりと、使い分けが可能です。ただし、手数料は「マイナ免許証のみ」と比べると高くなり、住所変更手続きは従来どおり警察への届け出が必要です。
3. 運転免許証のみ
従来どおり、プラスチックカード型の免許証のみを保持する方法です。料金も2枚持ちよりは安価ですが、「マイナ免許証のみ」よりは高い設定です。これまで通りの使い勝手が維持でき、未対応サービスで困ることもありません。しかし、ワンストップでの住所変更やオンライン講習など、マイナ免許証ならではの利便性を利用できないことはデメリットといえます。
有効期限について
マイナンバーカードは通常10年(未成年は5年)の有効期限があり、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書にはそれぞれ有効期限が設定されています。一方で、運転免許証には「免許の有効期限」が設定されており、マイナンバーカードと運転免許証の有効期限は異なります。マイナ免許証の場合、券面に有効期限は表記されないため、マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリを使って確認することが重要です。
特に、マイナンバーカードを更新したタイミングでマイナ免許証の情報が自動的に引き継がれない現状では、「マイナンバーカードを更新したら、もう一度運転免許センターなどでICチップへの記録をしてもらう」という手続が必要になります。2025年秋頃を目標に、更新時に自動的に免許情報を引き継げるシステムが導入される予定ですが、それまでは手動での再記録が避けられません。
マイナ免許証の利用方法
利用を開始するための手続
マイナ免許証としての利用を始めるには、2025年3月24日以降に運転免許センターや一部の警察署で行う手続が必要です。新規取得や更新だけでなく、住所変更や再交付などのタイミングでもマイナ免許証への切り替えが可能なので、希望する方は事前に予約を取り、運転免許センターや警察署で申請を行いましょう。
なお、70歳未満の方が更新手続と同時にマイナ免許証を取得する場合、都道府県によっては「運転免許手続予約サイト」や自動音声予約ダイヤルから事前予約が必要となります。再交付や失効などの際に切り替えを行う場合は、「行政手続オンライン」で予約するなど、手続内容によって予約方法が異なる場合があります。詳細は各都道府県警察のウェブサイトを確認してください。
マイナ免許証情報の確認方法
マイナ免許証には、券面に免許の有効期限や種別などは印字されません。そこで、マイナ免許証の情報を確認したい場合は以下の2つの方法があります。
- マイナポータルでログインし、署名用電子証明書(暗証番号6〜16桁)の情報を用いて免許情報を確認する
- スマートフォンやパソコンに「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールし、暗証番号(数字4桁)を入力してICチップに記録された免許情報を読み取る
レンタカー店などが利用者の免許情報を確認する場合にも、この読み取りアプリが役立ちます。アプリの普及に伴って、マイナ免許証対応サービスが今後広がる見込みです。
よくある質問
Q1. マイナ免許証を紛失した場合、どうすればいいですか?
マイナンバーカードを紛失した場合と同様に、まずは「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へ電話して、一時利用停止の手続きを行ってください。24時間365日対応です。その後、必要に応じてマイナンバーカードの再発行を申請し、免許情報を再度記録する手続を運転免許センター等で行うことになります。
また、マイナ免許証のみを持っていた方が紛失した場合、すぐに車を運転したい場合は、従来の運転免許証を再発行してもらうことも可能です。
Q2. 国外運転免許証が必要ですが、マイナ免許証だけで大丈夫でしょうか?
渡航先の国によっては、従来の運転免許証を提示しないと国外運転免許証の申請ができない場合があります。マイナ免許証のみを持っていて「やはり従来の免許証も欲しい」という場合は、所定の手続きを踏めば後から2枚持ちに変更することも可能です。ただし、手続には予約や再交付の手数料がかかる場合があるため、海外で運転を想定される方は最初から2枚持ちを選んでおくことも検討してください。
Q3. マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限が切れても、マイナ免許証は使えますか?
署名用電子証明書の有効期限は、マイナ免許証の「運転資格そのもの」に直接影響するわけではありません。ただし、オンライン講習や住所変更のワンストップサービスなど、電子証明書を用いるサービスには影響が出ることがあります。期限が近い場合は早めに更新しましょう。
Q4. マイナ免許証のみを選んだ後、やっぱり従来の運転免許証が欲しくなった場合は?
所定の手続きを行うことで、後から運転免許証の交付を受けることが可能です。具体的には運転免許センターや警察署で「保有状況の変更」を申請し、再度手数料を支払うことで発行が受けられます。
Q5. マイナ免許証はスマートフォンに搭載できますか?
マイナンバーカードのスマートフォン搭載(いわゆる「スマホマイナンバー」)は実現されていません。そのため、マイナ免許証をスマートフォンとして利用することはできず、物理カードのマイナンバーカードを携帯する必要があります。将来的にはスマホ搭載の検討が進められているため、今後に期待しましょう。
Q6. マイナンバーカードを更新したら、マイナ免許証はどうなりますか?
マイナンバーカードの更新(有効期限切れなど)によってカードが変わると、新たなICチップには免許情報が記録されていない状態になります。そのため、更新後のマイナンバーカードをマイナ免許証として機能させるには、再度免許情報の記録手続を行う必要があります。2025年秋頃を目処に自動引き継ぎできるシステムの導入が予定されていますが、それまでは手動での対応が必要です。
まとめ
2025年3月24日から始まるマイナ免許証は、行政のデジタル化を推し進める取り組みの一環であり、オンライン講習や住所変更のワンストップサービスなど、便利な機能を多数備えています。一方で、一部のレンタカーやカーシェアなどのサービスでは、マイナ免許証での本人確認が難しい場合があるほか、海外運転やマイナンバーカードの更新手続などいくつかの注意点も存在します。
運転免許証を「マイナ免許証のみ」にするのか、「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」にするのか、それとも「運転免許証のみ」で従来どおりに維持するのかは、各自の生活スタイルによって最適解が変わってきます。特に、海外渡航の予定がある方や、免許証を使ったサービス(レンタカー・カーシェア等)を利用する機会が多い方は、早まって「マイナ免許証のみ」に切り替えてしまうと不便が生じる恐れがあります。また、マイナンバーカードの有効期限が近い方は、先にカードを更新しておくことで二度手間を防ぐことができるでしょう。
マイナ免許証の導入は、今後のデジタル社会において大きな一歩となる取り組みです。将来的にはマイナンバーカードのスマートフォン搭載なども予定されており、より利便性の高いサービスが期待されます。ご自身のニーズや利用状況を考慮しながら、最適な免許証の持ち方を選択してください。