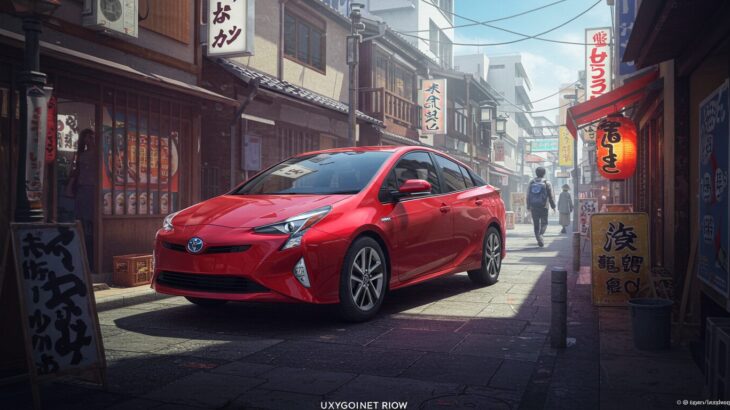免許を取って、初めて一人で路上に出た日のこと、覚えていますか?
ハンドルを握る手に汗がにじみ、周りの車の流れに乗るだけで精一杯。カーナビの案内に耳を傾け、標識や信号に目を配り、歩行者や自転車がいないかキョロキョロ…。運転というのは、本当に多くのことを同時にこなさなければならない、とても複雑な作業ですよね。
特に、運転に慣れていない初心者の方や、久しぶりにハンドルを握るペーパードライバーの方が「ヒヤリ」としやすい場面の一つが、「信号のない横断歩道」ではないでしょうか。
横断歩道の手前で、向こう側へ渡ろうかどうしようか迷っているように見える歩行者。
「あ、これ、止まるべきなのかな?」
「でも、後ろの車も来てるし、急に止まったら危ないかも…」
「歩行者さんも、こっちの車に気づいて待ってくれているみたいだし、このまま行っちゃおうか…」
ほんの数秒の間に、頭の中でたくさんの考えが駆け巡る。そして、迷った末に、そろそろと通過してしまった…なんて経験、正直に言ってありませんか。
その一瞬の迷い、そして「ヒヤリ」とした気持ち。この記事は、そんなあなたのために書きました。
自動車メディアのプロとして、専門用語は一切使わずに、この「信号のない横断歩道」のルールを、どこよりも分かりやすく、そして丁寧にご説明します。この記事を読み終える頃には、あなたはもう横断歩道の前で迷うことはありません。「止まるべきか、行くべきか」の判断に自信がつき、スマートで安全な運転ができるようになっているはずです。
一緒に、歩行者にも、そして自分自身の心にも優しい運転の第一歩を踏み出しましょう。
日本の現実。「止まらない」車がまだ半数以上もいる
まず、あなたが「止まるべきか迷う」と感じてしまうのは、決してあなた一人のせいではない、ということを知ってください。なぜなら、日本の道路には、残念ながら「止まらない」車があふれているのが現実だからです。
自動車ユーザーの団体であるJAF(日本自動車連盟)が毎年行っている、非常に興味深い調査があります。それは、「信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている時、一時停止する車がどれくらいいるか」という全国調査です。
2023年の調査結果によると、一時停止した車の割合は、全国平均で45.1%でした。
この数字、どう思われますか?
前年よりは改善しているものの、依然として半数以上の車、つまり2台に1台以上が、歩行者がいるにもかかわらず止まらずに通過してしまっているのです。これでは、歩行者側も「車は止まってくれないものだ」と思ってしまい、渡るのをためらってしまうのも無理はありません。
では、なぜ多くのドライバーは止まれないのでしょうか。その理由として、よく挙げられるのが次のような心理です。
・後続車が気になる
「自分が急に止まったら、後ろの車に追突されるかもしれない」「迷惑だと思われるかもしれない」というプレッシャーを感じてしまう。
・歩行者の意図が読めない
歩行者が本当に渡りたいのか、それともただ立っているだけなのか、判断に迷ってしまう。
・「行かせてくれた」という思い込み
歩行者が立ち止まってくれたのを見て、「どうぞ、お先に」と道を譲ってくれたのだと、自分に都合よく解釈してしまう。
・ルールの知識が曖昧
そもそも、「歩行者がいたら絶対に止まらなければならない」というルールを、はっきりと認識していない、あるいは忘れてしまっている。
あなたも、これらの気持ちのどれかに、少しだけ心当たりがあるかもしれません。しかし、これらの理由はすべて、道路交通法という絶対的なルールの前では通用しません。次に、そのルールについて、改めて基本から確認していきましょう。
これだけは覚えて!横断歩道の絶対的なルール
「横断歩道は歩行者優先」という言葉は、誰もが教習所で習ったはずです。では、具体的に法律ではどのように定められているのでしょうか。難しく考える必要はありません。ポイントはたったの2つです。
道路交通法の第38条には、ドライバーが守るべき義務が書かれています。それを、ものすごく簡単に要約すると、次のようになります。
1. 横断中、または横断しようとする歩行者が「いる」場合
これは、「絶対、一時停止しなければならない」という義務です。
横断歩道に近づいた時、明らかに道を渡ろうとしている人がいる。その場合は、選択の余地はありません。あなたは、横断歩道の手前(停止線があれば、その手前)で、必ず一時停止しなければなりません。そして、その歩行者が安全に横断するのを待つ義務があります。
「歩行者がこっちに気づいて止まってくれたから」とか、「まだ距離があるから大丈夫だろう」といった、ドライバー側の勝手な判断は一切認められません。渡ろうとしている人がいる、その事実だけで、あなたには「停止義務」が発生するのです。
2. 横断しようとする歩行者が「いるかいないか、明らかでない」場合
これは、「横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなければならない」という義務です。
例えば、横断歩道の脇に人が立っているけれど、スマホを見ていて渡る素振りがない。あるいは、駐車している車の陰になっていて、人がいるかどうかよく見えない。
こんな時は、「まあ、いないだろう」と速度を上げて通過するのはNGです。もし、その人が急に渡り始めたり、車の陰から子供が飛び出してきたりした場合に、安全に停止できるようなスピードまで、あらかじめ速度を落として横断歩道に近づかなければならない、と定められています。
つまり、まとめるとこうなります。
横断歩道に近づいたら、まずは「誰か渡ろうとしていないかな?」と注意する。
↓
渡ろうとしている人がいたら、必ず止まる。
↓
いるかいないかハッキリしないなら、すぐに止まれるスピードで進む。
そして、歩行者が「いないことが明らかな場合」にのみ、そのままの速度で通過することが許されるのです。この「いないことが明らか」という点が重要です。少しでも「いるかもしれない」と思ったら、それはもう「明らか」ではありません。
このルールは、車社会における、最も基本的な「思いやり」の形だと言えるでしょう。
「うっかり」では済まされない。一時停止違反の重いペナルティ
「でも、もしうっかり止まれずに通過してしまったら、どうなるの?」
そんな疑問も湧いてきますよね。この違反は、「横断歩行者等妨害等」という、れっきとした交通違反です。そして、そのペナルティは、あなたが思っている以上に重いものかもしれません。
違反点数と反則金
信号のない横断歩道で一時停止義務を怠った場合、次のような罰則が科せられます。
・違反点数:2点
・反則金:普通車の場合 9,000円
「なんだ、その程度か」と思われたでしょうか? もしそうなら、その考えは少し危険です。この「2点」と「9,000円」が、あなたのカーライフに与える影響は決して小さくありません。
ゴールド免許がブルーになる
もしあなたが、これまで無事故・無違反でゴールド免許を持っていたとしても、この違反で捕まってしまうと、次回の免許更新では「ブルー免許」になってしまいます。ブルー免許になると、免許の有効期間が短くなったり、更新時の講習時間が長くなったりします。
自動車保険料が上がる可能性も
自動車保険の中には、「ゴールド免許割引」を適用しているものがあります。ブルー免許になることで、この割引が適用されなくなり、年間の保険料が数千円から、場合によっては一万円以上も高くなってしまう可能性があります。たった一度の違反が、数年間にわたって経済的な負担となって跳ね返ってくるのです。
何よりも怖いのは「事故」のリスク
そして、点数や反則金よりも何よりも恐ろしいのは、人身事故を起こしてしまうリスクです。
もし、あなたが止まらなかったことで歩行者と接触し、怪我をさせてしまったら、それはもう「交通違反」では済みません。「交通事故」として、非常に重い責任を問われることになります。
・刑事上の責任:自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪など)に問われ、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
・行政上の責任:違反点数が加算され、免許停止や免許取り消しといった重い処分が下されます。
・民事上の責任:怪我をさせてしまった相手への治療費や慰謝料など、数千万円、場合によっては億単位の高額な損害賠償を請求される可能性があります。
横断歩道上の事故は、ドライバー側の過失が非常に大きいと判断されます。「歩行者が急に飛び出してきた」という言い分は、ほとんど通用しません。
たった9,000円の反則金を惜しんだばかりに、あなたの人生そのものを狂わせてしまうほどの、取り返しのつかない事態を招く可能性があるのです。
もう迷わない!「止まるべきか」を判断する具体的なコツ
ルールや罰則の重さは理解できた。でも、一番知りたいのは「じゃあ、どうすればあの迷いをなくせるの?」ということですよね。
ご安心ください。ここからは、運転初心者の方が実践できる、具体的な判断のコツを3つ、ご紹介します。これを意識するだけで、あなたの運転は劇的に変わるはずです。
コツ1:道路の「ひし形マーク」を心の準備の合図にする
横断歩道の手前の道路に、ひし形のマーク(◇)が描かれているのをご存知ですか? これは、「この先に横断歩道がありますよ」という、ドライバーへの予告サインです。
このマークが一つ見えたら、「そろそろ横断歩道だ。誰かいないかな?」。二つ目のマークが見えたら、「よし、いつでも止まれるように、少しアクセルを緩めよう」。
このように、「ひし形マーク」を、心の準備と運転操作を切り替えるスイッチにするのです。これだけで、横断歩道への接近に余裕が生まれ、歩行者の発見がずっと楽になります。
コツ2:歩行者の「渡りたいサイン」を読み取る
「歩行者が渡るか分からない」という悩みは、歩行者の些細なサインを読み取ることで、かなり解消できます。次のような様子の人がいたら、「渡りたい可能性が高い」と判断しましょう。
・左右をキョロキョロと確認している
・車道のほうへ一歩、足を踏み出そうとしている
・車の流れが途切れるのを待っているように見える
・横断歩道の前で、明らかに立ち止まっている
特に、お子さんやお年寄りは、車の接近に気づいていなかったり、距離感の判断が苦手だったりすることがあります。また、最近ではイヤホンで音楽を聴いていたり、スマートフォンを操作していたりして、周りへの注意が散漫になっている歩行者も少なくありません。
「相手が避けてくれるだろう」という期待は捨てましょう。「相手はこちらに気づいていないかもしれない」という前提に立ち、こちらから先に危険を予測してあげることが、事故を防ぐ最大の秘訣です。
コツ3:判断に迷ったら、答えは100%「止まる」
そして、これが最も重要で、最もシンプルな解決策です。
「これ、どうしようかな…? 行けるかな…? 止まるべきかな…?」
もし、あなたの頭の中に、一瞬でもこの「迷い」が生まれたら、その時の正解は、100%、絶対に「止まる」です。
後続車が気になるかもしれません。でも、あなたが法律に従って正しく停止しているのなら、何も気にする必要はありません。もしそれで追突してくる車がいるとしたら、悪いのは十分な車間距離を取っていなかった後続車です。
あなたが勇気を持って止まることで、歩行者は安心して道を渡ることができます。その姿を見た後続車のドライバーも、「あ、そうか、ここは止まらないといけないんだな」と、ルールを再認識するきっかけになるかもしれません。
あなたのたった一つの「止まる」という優しいアクションが、その道路の安全な交通文化を作っていくのです。そう考えると、少しだけ、誇らしい気持ちになりませんか?
もっとスマートに!後続車にも優しい停止と再発進
最後に、ただ止まるだけでなく、周りの車にも配慮した、よりスマートな運転のコツをお伝えします。これができれば、あなたはもう初心者ではありません。
停止する時:早めの予告と、ふんわりブレーキ
歩行者を見つけて「止まろう」と決めたら、いきなり急ブレーキを踏むのは危険です。後続車を驚かせ、追突を誘発する原因になります。
まずは、アクセルから足を離し、エンジンブレーキで自然に減速します。そして、ブレーキペダルを数回に分けて軽く踏む「ポンピングブレーキ」をすれば、ブレーキランプが点滅し、後続車に「これから止まりますよ」という合図を送ることができます。
そして、停止線に向かって、ふんわりと、同乗者の頭がカクンとならないような、優しいブレーキを心がけましょう。
再発進する時:最後の最後まで安全確認
歩行者が渡り終えたからといって、すぐにアクセルを踏むのは早計です。再発進する前にも、確認すべきポイントがあります。
・歩行者は完全に歩道を渡り切ったか?
・対向車線の車の陰から、別の歩行者や自転車が飛び出してこないか?
・渡って行った歩行者が、忘れ物をして引き返してくる可能性はないか?
特に、横断する歩行者の陰になって、反対側から渡ってくる次の歩行者が見えなくなっているケースは非常に危険です。一呼吸おいて、左右の安全をもう一度しっかりと確認してから、ゆっくりとスムーズに車を発進させましょう。
まとめ
信号のない横断歩道。それは、ドライバーの「交通ルールへの理解度」と「他者への思いやり」が、最も分かりやすく表れる場所と言えるかもしれません。
この記事でお伝えしてきた、大切なポイントをもう一度振り返ってみましょう。
・横断しようとする歩行者がいたら、一時停止は「絶対的な義務」である。
・違反すれば、点数や反則金だけでなく、ゴールド免許を失ったり、保険料が上がったりと、多くのものを失うことになる。
・何よりも、事故を起こしてしまえば、取り返しのつかない事態になる。
・「ひし形マーク」を合図に心の準備をし、「渡りたいサイン」を読み取る。そして、少しでも判断に迷ったら、答えは必ず「止まる」。
・あなたが勇気を持って止まることで、歩行者の安全が守られ、社会全体の交通安全意識も高まっていく。
運転は、技術だけでするものではありません。周りの状況を予測し、危険を未然に防ぎ、交通社会に参加するすべての人を尊重する「心」でするものです。
横断歩道の前で止まる一台の車。それは、歩行者への優しさの表れであると同時に、あなた自身と、あなたの大切な同乗者を守るための、最も確実な安全行動なのです。
明日から、横断歩道に近づいたら、今日お話ししたことを少しだけ思い出してみてください。きっと、今までよりもずっと落ち着いて、自信を持ってハンドルを握れるようになっているはずです。