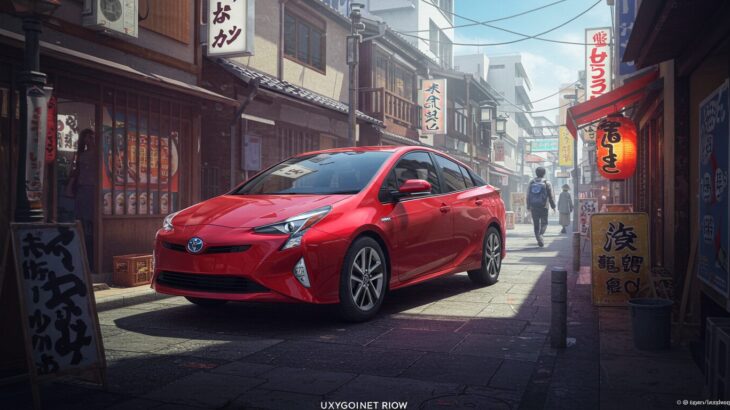交通事故の過失割合とは?
交通事故が起きてしまった場合、当事者同士が負う責任の大きさを示す指標として「過失割合」が用いられます。過失割合とは、ざっくり言うと「事故によって生じた損害のうち、どの程度を誰が負担すべきか」を割合で示したものです。たとえば「相手が7割、自分が3割」というように表されます。
過失割合は、最終的には「自分が支払うべき賠償金額」や「自分が受け取るべき賠償金額」に直結するため、非常に重要な意味を持ちます。一度示談でこの割合を決めてしまうと、よほどのことがない限り後から覆すことは難しくなるため、事故が起きた際には、過失割合についてしっかり理解し、妥当な数字で合意できるようにすることが大切です。
過失割合を決めるのは誰?
「過失割合は警察が決める」と思われがちですが、実際には警察は事故状況を確認し、加害者・被害者の関係を整理する役割を担うだけで、過失割合を決定する権限は持っていません。最終的には、事故の当事者同士が話し合いによって過失割合を合意します。
もっとも、当事者双方が任意保険に加入している場合、多くは「保険会社同士の交渉」を通じて決まるのが一般的です。ただし、過失割合が100:0(いわゆる「もらい事故」)に近いケースでは、被害者側の保険会社が示談交渉に直接関与できない(非弁行為にあたる可能性がある)こともあります。そのようなときは、被害者本人と相手の保険会社の担当者が交渉し、最終的な割合を詰めていく流れになります。
また、当事者や保険会社同士の話し合いで解決できないほど意見の相違が大きい場合には、裁判所の調停や裁判という法的手段によって決着させることもあります。たとえば、被害者側が一方的に「相手側が100%悪い」と主張し続けて合意がまとまらない場合や、加害者側の提示する過失割合が不当に高いと感じる場合などがその典型です。こうした法的手段を取るか否かは、事故後の対応スケジュールや損害の程度なども踏まえて総合的に判断する必要があります。
過失割合の具体的な決定プロセス
過失割合が「当事者同士の合意」で決まるといっても、まったく基準がなく、ただ感覚的に決められるわけではありません。実際には、以下のようなプロセスを踏むことが一般的です。
事故状況の事実認定
まず、どのような状況で事故が発生したのかを正確に把握し、当事者間で事実関係を整理します。警察に提出した「実況見分調書」や、当事者がその場で撮影した写真・動画、ドライブレコーダーの映像、さらには目撃証言などを材料に、以下の点を明らかにしていきます。
– どの車が、どのタイミングで、どの場所にいたか
– 交差点の信号機の色は何色だったか
– 一時停止や減速の有無
– 道路の幅や優先関係
– 天候・視界の状況
事故状況に関する認識が食い違っているときは、できるだけ客観的な証拠(ドライブレコーダー映像や複数人の目撃証言など)を集めて、事実認定を行うことが重要です。ここで誤った事実認定がなされると、過失割合自体も正しく算定できなくなります。
基本過失割合の確認
次に、事故の形態や類型をもとに「基本過失割合」を確認します。これは、過去の裁判例や専門書(たとえば『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』など)を根拠にして示されている基準となる数字です。「追突事故」「右左折車と直進車の事故」「信号のない交差点での出会い頭事故」など、ケースごとに一般的な参考値が存在します。
たとえば「信号のない交差点で、広い道路を直進中の車と、狭い道路から右折しようとした車が衝突した」ケースなら、広い道路を走行していた車の基本過失割合は2割(20%)、右折車の基本過失割合は8割(80%)という形で、書籍などに示されているのです。この数字はあくまで「基本」の割合なので、実際の事故状況に合わせて調整が行われることになります。
修正要素の検討
基本過失割合が確認できたら、「修正要素」を考慮し、最終的な過失割合を算定します。修正要素には様々なケースがありますが、具体的には以下のような点が該当します。
– 相手車両が著しく速度超過していた
– 一方の車両がハザードランプを点灯して徐行していた
– 夜間で視界が悪かったが、ヘッドライトの照射範囲などで回避が可能だったか
– ドライバーが飲酒状態や無免許運転だった
– 天候が急変し、路面が極端に滑りやすかった
これらの要因を加味して、被害者・加害者の一方に過失を「加算」したり「減算」したりして、最終的な割合を調整します。たとえば、本来なら広い道路を走っていた車が優先でも、極端な速度超過が証明されれば「そもそも安全運転の義務を怠っていた」と判断され、過失が増える可能性があります。
当事者の合意による確定
以上のステップを踏んで導き出された過失割合を当事者同士で確認し、合意に至った段階で、示談が成立します。示談書には過失割合を明示的に記載するケースもあれば、「支払うべき損害賠償金の金額」で事実上、過失割合が確定するケースもあります。
示談で合意した後に「やはり納得がいかない」と感じても、基本的にはやり直しが利かないため、交渉段階で十分に検討することが非常に重要です。
双方に過失があるときの過失相殺について
交通事故では、一方が100%責任を負うケースばかりではありません。むしろ、ほとんどの場合で「双方に何らかの落ち度がある」と判断され、当事者双方の過失割合を元に「過失相殺」が行われます。過失相殺とは、被害者側にも過失がある場合に、被害者側が受け取る賠償金を当該過失割合分だけ減らす仕組みです。
たとえば、以下のような事例を考えてみましょう。
– 過失割合:被害者15%、加害者85%
– 被害者が被った損害額:500万円
– 加害者が被った損害額:100万円
この場合、被害者は本来なら500万円の損害について加害者に賠償を求められますが、「自分にも15%の落ち度がある」とされるので、その分を減額され、最終的には85%の425万円が賠償対象になります。一方、加害者も自分の損害100万円のうち15%(15万円)を被害者に請求できることになり、最終的には425万円と15万円の差額である410万円を加害者が被害者に支払う形になります。
このように、過失相殺を行うことによって、当事者の公平性を図るのが日本の交通事故処理における基本的な考え方です。ただし、当事者同士の話し合いで「相殺ではなく一方が一括して賠償する」形をとる場合もあり、支払い方法は必ずしも一律ではありません。実務上は、保険会社同士が計算をし、差額をまとめて支払うパターンが多く見られます。
事故タイプ別の過失割合の例
過失割合は事故の態様や当時の状況によって変動しますが、大まかには以下のようなパターンに分類して検討されることが多いです。
自動車同士の事故
高速道路での追突事故や、交差点での右左折車と直進車の衝突、信号のない交差点での出会い頭事故などが典型的な例です。たとえば追突事故の場合は、基本的に「後ろから追突した車両」に重い過失があると考えられるため、「追突側:追突された側=80:20」「90:10」などが基本過失割合として示されることがよくあります。ただし、追突された側にも急ブレーキや急停車の理由があった場合などには修正されることがあります。
自動車対バイクの事故
バイクは自動車に比べて死角に入りやすく、また車体が軽いため転倒などのダメージも大きくなりがちです。このため、自動車側が「バイクが見えづらい状況だった」としても、注意義務違反を指摘されることがあります。基本的な過失割合は、自動車同士の事故よりも「自動車側が大きめ」に設定されやすいケースもあるため、注意が必要です。
自動車やバイク対自転車の事故
自転車と自動車の事故では、自転車の運転者に交通ルールの知識不足があるケースが少なくありません。一時停止をしなかったり、無灯火で夜間走行していたりといった事情が過失割合の判断に影響します。一方で自動車側は、より大きい車両を運転している以上「より高い注意義務を負うべき」という考え方があり、過失割合の検討では自動車に大きな責任が課されやすいことも特徴的です。
自動車対歩行者の事故
歩行者との事故の場合は、歩行者が交通ルールを破っている場合でも、自動車側には「より一層の安全配慮義務」が課される傾向にあります。たとえば夜間の横断であっても、自動車側がヘッドライトをきちんと照射し、歩行者を早期に発見できなかったのかが問われるケースが多いです。結果的に、歩行者側に明らかな落ち度があっても、自動車側の過失が大きめに設定されることが珍しくありません。
過失割合に不満がある場合の対処法
過失割合は示談交渉の根幹をなす要素なので、もし相手(または相手の保険会社)から提示された過失割合に納得できない場合は、すぐに示談に応じずに「理由を明確にして異議を申し立てる」ことが大切です。以下のような点を丁寧に主張していく必要があります。
事実認定が誤っている場合
そもそもの事故状況が間違って認定されていると感じる場合は、ドライブレコーダー映像、目撃者の証言、警察の作成した実況見分調書などをもとに、どこがどのように誤りなのかを主張します。たとえば「自分は確実に一時停止したはずなのに、相手はそれを認めない」というケースでは、一時停止した証拠を出す、ドライブレコーダーに記録が残っていないか確認するなど、客観的な裏付けを示すことが重要です。
過失割合の算定基準が誤っている場合
事故状況自体は合意しているものの、そこから導き出される過失割合が不当だと感じるケースもあります。たとえば、「基本過失割合は70:30のはずなのに、なぜか90:10だと提示された」といった場合です。このようなときは、専門書や過去の判例を示しながら「適切な判例はこれであり、修正要素もこう考えるべき」という形で交渉を進める必要があります。
示談交渉が決裂した場合の手段
当事者同士、あるいは保険会社同士の示談交渉が難航したときは、ADR(裁判外紛争解決手続)や裁判所の調停、さらには民事訴訟を検討することもできます。たとえば、「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」などの機関が、無料もしくは低額の費用であっせんや和解の仲介を行っている場合があります。裁判所での調停や裁判になると時間や費用がかかる可能性がありますが、正当な権利を守るために必要な場合もあるでしょう。
また、自動車保険の「弁護士費用特約」を付帯していれば、弁護士への依頼費用を保険でカバーできるケースが多いです。交渉が難航すると感じる前に、あらかじめ保険の契約内容を確認しておき、必要に応じて弁護士に相談するのも有効な手段です。
過失割合の決定とドライブレコーダー
交通事故の過失割合を決める際には、「どちらがどの程度、事故防止に配慮していたか」が大きな争点になります。口頭での主張だけでは「信号は青だった」「いや赤だった」といった水掛け論になりがちですが、ドライブレコーダーに記録された映像は非常に有力な証拠となります。実際の法的手続でも、ドライブレコーダー映像が採用され、被害者の主張が認められた例は少なくありません。
たとえば、以下のような点で役立ちます。
– 事故直前の信号の色
– 交差点への進入速度
– 一時停止標識がある場所での停車の有無
– 相手車両の急な車線変更や割り込み
また、最近は「安全運転支援機能」を搭載したドライブレコーダーが増え、通信機能により事故発生時に自動で通報したり、専用のオペレーターとやりとりできたりする商品も登場しています。こうした機能によって事故対応をスムーズに進めやすくなるだけでなく、客観的な事故証拠を即座に記録できるメリットがあります。
三井住友海上でも、ドライブレコーダーと連動した自動車保険を提供しており、万が一の事故後におけるスピーディな対応が期待できます。事故直後は誰しもパニックになりがちですが、頼れるサポートや客観的な証拠があれば、過失割合の決定で不利になるリスクを減らせるでしょう。ドライブレコーダー付き自動車保険を活用すれば、示談交渉の際に強力な武器となる可能性があります。
まとめ
交通事故の過失割合は、当事者それぞれが「どれだけ事故防止に配慮を欠いていたか」を示す数字であり、最終的な損害賠償の金額を大きく左右します。警察はあくまでも事故状況を取りまとめる役割であり、実際に過失割合を決定するのは当事者間の話し合いです。双方が任意保険に加入しているケースでは保険会社同士の交渉で決まることが多いですが、認定された過失割合に納得がいかない場合は、示談を締結する前に必ず異議を申し立てましょう。
過失割合の判断基準としては、過去の裁判例や専門書が参考にされ、事故態様ごとにある程度の「基本過失割合」が示されています。そこに修正要素を加えて最終的な数字を導き出すため、速度超過や一時停止違反など、事故状況に特有の事情がある場合はしっかり主張しなければなりません。
また、事故直後は冷静さを失いがちですし、相手側との交渉が進むにつれて「言った」「言わない」の水掛け論に陥るリスクもあります。そんなとき、ドライブレコーダーの映像は非常に心強い証拠になります。加えて、自動車保険の弁護士費用特約なども備えておけば、万が一話し合いが決裂した場合に迅速に弁護士へ相談し、法的手続に移行しやすくなるでしょう。
交通事故は誰にとっても突然の出来事です。もしもの時に備えるためには、日ごろから安全運転を心がけると同時に、万が一の際に備えた自動車保険の内容を充実させておくことが重要です。三井住友海上のドライブレコーダー付き自動車保険は、事故の状況証明に役立つだけでなく、事故時のサポート体制も整えています。必要な備えを早めに検討しておけば、いざというときのリスクを大きく減らせるはずです。
過失割合の計算ひとつで、受け取る金額・支払う金額が大きく変わるのが交通事故の怖いところです。事故後に後悔しないためにも、保険の見直しやドライブレコーダーの設置、交渉スキルの把握など、できる準備はあらかじめしておきましょう。長引く示談交渉をスムーズに進めるためにも、正確な事故状況の把握と、客観的証拠の確保が何よりもカギとなります。