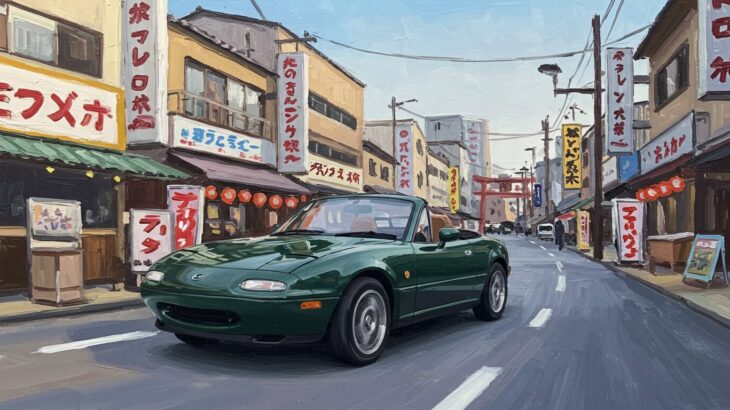- 1. クルマ運転中に地震が起こる可能性と危険性
- 2. 大きな揺れを感じたら急ハンドル・急ブレーキを避けて安全に停止
- 3. クルマを停止したらすぐに車外に飛び出さず、まずは揺れが落ち着くのを待つ
- 4. 揺れが収まった後も、周辺状況と道路状況をよく確認
- 5. もしクルマを置いて避難する場合はキーを車内の目立つ場所に
- 6. 高速道路で地震が発生した場合の注意点
- 7. 地震発生後のクルマ利用と注意点
- 8. 地震発生直後の情報収集がカギ
- 9. 「交通の教則」が示す大地震時の運転者の措置
- 10. 運転再開の判断と注意すべきポイント
- 11. 運転者として備えておきたいもの
- 12. 大地震に際して運転者が覚えておくべき大原則
- 13. まとめ
クルマ運転中に地震が起こる可能性と危険性
日本は世界の中でも地震が頻発する国として知られています。海や山など豊かな自然に恵まれている反面、地震や津波、台風、豪雨、火山噴火といった自然災害が多く発生する地域でもあります。とくに大規模な地震は予測が難しく、走行中に遭遇してしまうこともあり得ます。災害が起きた際にはクルマの運転を控えるのが望ましいのは当然ですが、「もし運転中に強い揺れを感じた場合」はどう行動すればよいのでしょうか。
走行中は周囲のクルマも同じように突発的な事態に直面し、パニック状態に陥っているかもしれません。また、道路や高架の破損、信号機の停止、建造物の倒壊など、二次災害のリスクも一気に高まります。そこで大切になるのが、あらかじめ地震時の対処法を知っておき、いざというときに落ち着いて行動できるよう備えることです。ここからは、地震を感じた際の運転者の具体的な行動ポイントを詳しく解説していきます。
大きな揺れを感じたら急ハンドル・急ブレーキを避けて安全に停止
大地震の際、クルマの車体は激しく揺れ、ハンドルをとられるような感覚を受けることがあります。ちょうどタイヤがパンクしたときのような操作のしづらさを想像するとわかりやすいでしょう。しかし、そのときに慌てて急ブレーキを踏んだりハンドルから手を離したりすると、思わぬ事故を引き起こす危険性があります。
まずは、ハンドルをしっかり握り、揺れによってバランスが崩れないように運転操作を続けながら、徐々にスピードを落としましょう。同時にハザードランプを点滅させて周囲に注意を呼びかけることが重要です。パニックになると、後続車に気を配れないドライバーが出てくる場合もありますが、自分がハザードランプで合図を送ることで追突や接触事故を防ぎやすくなります。
そのうえで、安全を最優先に考え、可能なかぎり道路の左側へ寄せてクルマを停止させましょう。高速道路を走行中の場合でも、最寄りの安全なスペースや路肩を目指すのが基本です。高速道路に設置されている情報掲示板やラジオなどから流れる交通情報に注意しながら、周囲に危険が及ばないように停止位置を確保する必要があります。
クルマを停止したらすぐに車外に飛び出さず、まずは揺れが落ち着くのを待つ
クルマを止めた直後は、とにかく外へ避難しようと焦ってしまいがちです。しかし、大きな地震の際には、後続車も余裕をなくしているかもしれず、いきなり車外に出るのはかえって危険です。まずは揺れが収まるまで車内に留まりましょう。慌てて外へ飛び出すと、周囲の車両や落下物に巻き込まれるリスクがあります。
車内で待機しているあいだは、ラジオやテレビ、スマートフォンの災害情報アプリなどを活用して、地震情報や道路交通情報を収集してください。たとえば緊急地震速報が発せられた際には、追加の大きな揺れが来る可能性があるかなど、情報を把握しておくことは非常に大切です。もし揺れが長引いているようなら、まずは落ち着いて深呼吸をし、パニックを抑えるように意識しましょう。
揺れが収まった後も、周辺状況と道路状況をよく確認
地震が落ち着いてきたと感じても、まだ安心はできません。大規模な地震では、その後も余震が続いたり、道路が損壊していたり、高架道路が崩落していたり、火災が発生していたりと、二次災害の恐れがあるためです。信号機が停止している場合や電柱が傾いている場合もあります。周辺地域の被害状況をニュースやラジオから継続して収集し、少しでも危険を感じるようであれば、走行再開は慎重に判断する必要があります。
道路が崩落し始めた場合や大きく亀裂が入っているときは、ムリにクルマで移動しようとしてはいけません。クルマごと巻き込まれてしまうリスクが高く、非常に危険です。道路の通行止めや通行規制の情報があれば、それに従うことが大前提となります。焦って規制を無視した走行をすると、取り返しのつかない事故につながる可能性があるので、必ず自治体や交通機関からの指示に従いましょう。
もしクルマを置いて避難する場合はキーを車内の目立つ場所に
大地震の後、各地で通行規制や道路の崩落などが起きた場合、クルマの移動が困難になることがあります。また津波や火災などの二次災害が迫っている場合は、一刻も早く歩いて避難しなければならないケースもあるでしょう。こうした状況では、クルマを置いて離れざるを得ない場合があります。
その際は、道路の左側に寄せてエンジンを止め、サイドブレーキをしっかりかけ、窓を閉めてからドアはロックしないようにします。緊急車両が通行する際や、防災応急対策のためにクルマを動かす必要が出るかもしれないからです。エンジンキーは付けたままにするか、スピードメーターまわりなど「一目でわかる場所」に置いてください。貴重品は必ず自分で持ち出すことも重要です。
あわせて、車内にはメモなどで自分の氏名と連絡先を残しておくと、あとでクルマを移動する人や公的機関が確認しやすくなります。また、車検証は所有者を証明する重要書類なので、必ず持ち出しておくようにしましょう。
高速道路で地震が発生した場合の注意点
高速道路上で地震に遭遇すると、一般道以上に事故やトラブルが発生しやすくなります。高速走行中に急に揺れを感じれば、ハンドルをとられる感覚も強くなるでしょう。しかし、絶対に急ブレーキは踏まず、周囲のクルマと自車の挙動に意識を集中しながらスピードを徐々に落とし、ハザードランプをつけて減速していきます。
そのうえで、安全が確保できる場所、たとえば路肩や非常駐車帯と呼ばれる緊急停止スペースなどへ移動し、そこで停止しましょう。高速道路上では緊急地震速報が入ると、運営会社の情報掲示板やラジオ放送、さらには高速道路を管轄する事業者から注意喚起のアナウンスが流れる場合があります。これらの情報をしっかり確認して指示に従うことが何よりも大切です。
揺れが収まっても、高架区間やトンネル内、橋の部分などには大きな損壊が生じていないかを十分確認する必要があります。自力での走行再開が危険だと判断した場合は、通行止めや規制の情報に従いましょう。高速道路上でエンジンを止めて避難を余儀なくされる場合は、一般道路と同様、クルマをロックせずキーを付けたまま置いておきます。事故防止や二次被害拡大の回避のためにも、周囲の人や車両の通行を妨げない位置に停める配慮が必要です。
地震発生後のクルマ利用と注意点
大規模地震の直後には、被害が少ないエリアでも通行禁止や通行制限が敷かれることがあります。また「大規模地震災害に関する警戒宣言」が出された場合、クルマでの避難は原則として認められません。被害が大きい地域では緊急車両の円滑な移動を最優先するため、一般車の通行を制限することが多いからです。
そのため、やむを得ずクルマを使用する必要がある状況(津波からの避難など)を除き、大地震の後はできるだけクルマでの移動を控えるのが基本となります。やむを得ずクルマを使う場合でも、信号機の停止、道路の亀裂、倒れかけの電柱、瓦礫の散乱などに細心の注意を払いましょう。
地震発生直後の情報収集がカギ
多くのラジオ放送局やテレビ局は、緊急地震速報が発表された際に通常の番組を中断して地震情報を伝えます。これらのメディアを使うことで、走行中でもおおまかな震源情報や津波の有無、交通規制情報を得られる可能性があります。また、スマートフォンを利用するのであれば、災害情報アプリやSNSなどで周囲の状況を確認する手段も考えられます。
ただし、大地震の直後は回線が混み合い、電話や通信回線が使いづらくなる場合も多いです。そのため、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板の利用方法を家族や知人と普段から確認しておくことが重要です。万が一の時に連絡が取れなくなる可能性を考え、あらかじめ連絡手段を複数用意しておきましょう。
「交通の教則」が示す大地震時の運転者の措置
国家公安委員会告示の「交通の方法に関する教則」によると、クルマを運転中に大地震が発生したときには、次のように対応することが推奨されています。
– できるだけ急ハンドルや急ブレーキを避け、道路の左側に安全を確保したうえで停止する。
– 停止後はラジオなどで地震情報・交通情報を収集し、それに応じて行動する。
– 走行を再開する際は、道路損壊や信号機停止、障害物に注意する。
– クルマを置いて避難するときは、本来なら道路外の場所が望ましいが、やむを得ない場合は道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを停止。エンジンキーはそのまま、または車内のわかりやすい場所に置く。ドアはロックしない。
– 避難者や防災応急対策の人々の通行を妨げない場所を選ぶ。
これらの行動をとることで、自分の身を守るだけでなく、道路全体を使った応急対策や救助活動を円滑に行えるよう配慮することにもつながります。
運転再開の判断と注意すべきポイント
揺れが収まり、いったんは落ち着きを取り戻したように見えても、余震や津波、火災などの危険が引き続き存在する場合があります。ラジオや防災情報で危険度の高い区域がアナウンスされることもありますので、走行再開のタイミングは慎重に判断してください。具体的には以下の点をチェックするとよいでしょう。
1. 道路の損壊状況
道路に大きな亀裂や陥没、瓦礫などの障害物はないか確認します。夜間の場合はとくに見落としがちなので、街灯が落ちている可能性も考慮し、ヘッドライトを活用して周囲を見回すことが大切です。
2. 信号機の作動状況
停電により信号機が止まっている場合、交差点での事故リスクが大幅に上がります。通行できる状態であっても、見通しが悪いと衝突事故の危険性があるので、交差点に差し掛かったら必ず一時停止や徐行を徹底しましょう。
3. 周囲の交通規制や災害の有無
地震が原因での火災、崩壊しかけている建物の近く、津波の危険性がある沿岸部など、危険が予想される場所は避けるべきです。警察や自治体、道路管理者から出される通行止め情報に注意し、制限を守るのが最優先となります。
運転者として備えておきたいもの
いざというときに冷静に対処するためには、日ごろからの備えも重要です。大きな地震だけでなく、台風や豪雨などの災害においても共通する点がありますが、クルマの中に常備しておくと便利なアイテムをいくつか挙げておきます。
– 防災グッズ(簡易的な飲料水、非常食、救急セット、手袋、簡易トイレなど)
– 懐中電灯やヘッドライト(停電時の夜間走行や車外避難時に役立つ)
– モバイルバッテリー(スマートフォンの充電切れ対策)
– 毛布やタオル、簡易シートなど(防寒・応急措置に利用できる)
– 地図や道路マップ(電子機器が使えないときの予備対策)
また、家族や友人と連絡が途絶えた際には、災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板サービスなどを使う方法をあらかじめ共有しておくと安心です。クルマは便利な移動手段であると同時に、災害時にはむしろ動きを制限される可能性があることを理解し、可能な限り他の交通手段や避難経路も確保しておくとより安全です。
大地震に際して運転者が覚えておくべき大原則
ここまで紹介してきた内容をまとめると、運転中に大地震が発生した場合の大原則は以下のとおりです。
– 突然の揺れに驚いても、急ブレーキ・急ハンドルは厳禁。ハンドルをしっかり握り、少しずつ減速しながら、ハザードランプで周囲に注意を促す。
– 可能であれば道路の左側へゆっくり寄せ、安全を確認してから停止する。高速道路では非常駐車帯などを利用する。
– 揺れが大きいあいだは、むやみに車外に出ない。揺れがおさまるまで車内でラジオやスマートフォンを使って情報収集し続ける。
– その後も余震や道路損壊のリスクがあるため、走行再開は慎重に判断する。
– 通行規制や緊急車両のために道路が必要な場合は、クルマを置いて避難する選択も考える。その際はキーを車内のわかりやすい場所に置き、ドアをロックしない。
– 道路や交通機関からの情報を常にチェックし、無理な行動は避ける。
大きな地震が起きると、多くのドライバーが混乱し、道路状況も大きく変わります。しかし、しっかりと地震時の行動を覚えておけば、パニックに陥らず、より冷静に対処できるでしょう。
まとめ
大地震が発生した際の運転中の行動は、人生を左右するほど重大です。まずは急ブレーキや急ハンドルを避け、周囲へ注意を促しながら安全な場所に停止しましょう。揺れが収まるまでは車内で情報を収集し、無理に走り続けるのは禁物です。被害が大きい場合や緊急車両の妨げになる恐れがあるときはクルマを置いて避難する選択も必要です。普段から災害時の行動をイメージし、防災グッズを備えておくことで、いざというときに落ち着いた判断ができるようになります。