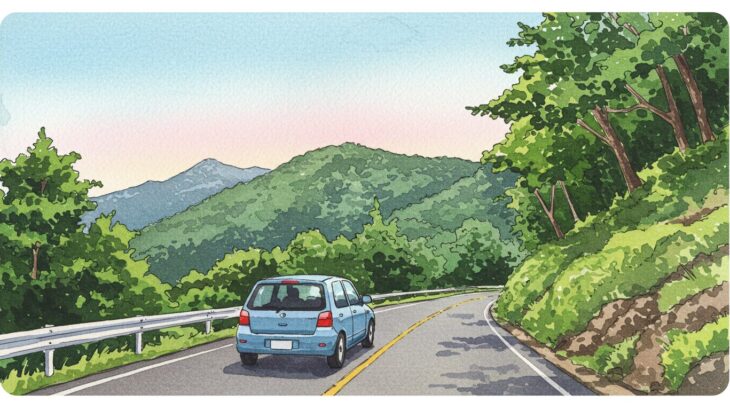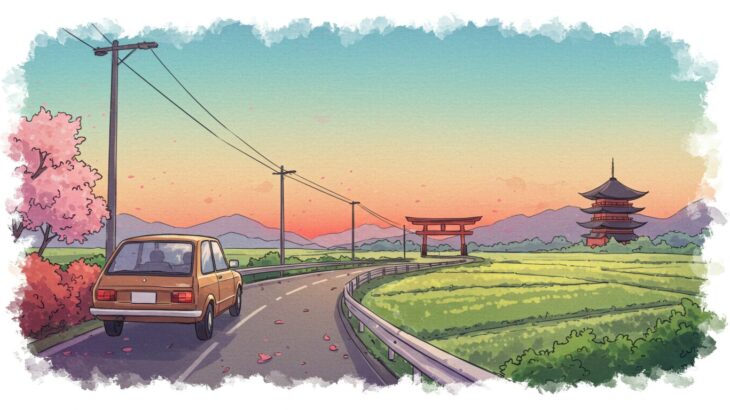愛車を自分好みにカスタマイズしたい。そんな想いは、車好きなら誰もが一度は抱くものではないでしょうか。しかし、その「カスタム」が、知らず知らずのうちに「違法改造」になってしまうケースが後を絶ちません。
「少しくらいなら大丈夫だろう」「見た目がかっこよければそれでいい」そんな軽い気持ちで行った改造が、実はとんでもないリスクを招く可能性があることをご存知でしょうか。
違法改造は、単に「車検に通らない」という問題だけではありません。警察からの厳しい罰則、そして万が一事故を起こしてしまった際に「自動車保険が使えない」という、まさに最悪の事態に陥る可能性を秘めているのです。
この記事では、運転免許を取りたての初心者の方や、久しぶりにハンドルを握るペーパードライバーの方にも分かりやすく、違法改造にまつわる様々なリスクと、安心してカーライフを楽しむためのポイントを、自動車のプロの視点から詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたの愛車とあなた自身を守るための正しい知識が身につくはずです。
そもそも「違法改造」とは? 合法カスタムとの境界線
まずはじめに、「カスタム」と「違法改造」の違いについて正しく理解しておく必要があります。この二つを分ける境界線はどこにあるのでしょうか。
国が定めた安全ルール「保安基準」
自動車には、安全に道路を走行し、環境にも配慮するために、国が定めた様々なルールがあります。これを「保安基準」と呼びます。具体的には、ライトの明るさや色、タイヤが車体からはみ出していないか、マフラーの音の大きさなど、非常に細かく規定されています。
簡単に言えば、この保安基準を満たしている範囲内で行うカスタマイズは「合法カスタム(ドレスアップ)」、保安基準から外れてしまうものが「違法改造」となります。
例えば、純正品とは違うデザインのホイールに交換する場合でも、保安基準で定められたサイズや取り付け方を守っていれば、それは合法的なカスタムです。しかし、車体からタイヤがはみ出してしまうようなホイールを装着すると、それは違法改造になってしまいます。
なぜ保安基準は存在するのか
なぜ、これほどまでに細かくルールが定められているのでしょうか。その理由は大きく分けて二つあります。
- 安全性の確保:自動車は、正しく使わなければ人の命を奪いかねない危険な乗り物です。ブレーキがしっかり効くこと、夜間にライトが正しく前方を照らすこと、周囲の車や歩行者に自車の動きを正確に伝えること。これら全てが確保されて初めて、安全な走行が可能になります。保安基準は、自分自身だけでなく、同乗者や他の交通参加者の安全を守るための最低限のルールなのです。
- 環境の保全:自動車から排出されるガスには、大気汚染の原因となる有害物質が含まれています。また、大きなマフラー音は騒音公害につながります。保安基準では、排気ガスの浄化性能やマフラーの音量についても厳しく定められており、地球環境や私たちの生活環境を守る役割も担っています。
つまり、カスタムを楽しむこと自体は何も悪いことではありません。しかし、その大前提として、この「保安基準」という社会的なルールを必ず守る必要があるのです。
【具体例で解説】これって違法改造?よくあるカスタム事例
ここでは、多くの方が行いがちなカスタムの中から、特に違法改造になりやすい事例を具体的に見ていきましょう。「これ、自分の車も危ないかも?」と感じる点がないか、チェックしてみてください。
タイヤ・ホイールのインチアップと「ハミタイ」
愛車の印象を大きく変えるパーツとして人気のタイヤ・ホイール交換。しかし、ここにも注意が必要です。
違法改造として最も多いのが、タイヤやホイールが車体の側面(フェンダー)からはみ出してしまう、通称「ハミタイ」です。タイヤがはみ出していると、回転するタイヤが歩行者などに接触する危険性が高まります。また、巻き上げた小石が後続車に飛んでいってしまうリスクも考えられます。
さらに、フェンダーの内側にタイヤが接触(干渉)し、ハンドル操作を妨げたり、最悪の場合タイヤが損傷してバースト(破裂)したりする危険性もあります。保安基準では、タイヤのはみ出しについて厳しく規定されており、たとえ数ミリでもはみ出していれば車検には通りませんし、警察の取り締まり対象となります。
マフラー交換と騒音・排ガス問題
迫力のあるエンジンサウンドに憧れて、マフラーを交換する方も多いでしょう。しかし、マフラーは音量や排気ガスの浄化性能に直結する重要なパーツです。
保安基準では、車種や年式ごとにマフラーの音の大きさ(近接排気騒音)の上限値が定められています。この基準値を超えるような爆音マフラーは、典型的な違法改造です。周囲に迷惑をかけるだけでなく、運転中のドライバーの集中力を妨げる可能性も指摘されています。
また、排気ガスを浄化するための装置(触媒、キャタライザー)を取り外してしまう改造も、絶対に行ってはいけません。これは環境に有害な物質をそのまま大気中に放出する行為であり、厳しい罰則の対象となります。
ライト(灯火類)の色や明るさの変更
ヘッドライトを明るいものに交換したり、ポジションランプやテールランプの色を変えたりするカスタムも人気ですが、灯火類は他の車や歩行者とのコミュニケーションを担う非常に重要な部分です。そのため、色や明るさ、点滅方法などが保安基準で細かく定められています。
・ヘッドライト、フォグランプ:色は「白」または「淡黄色」と定められています。青みがかったものや、極端にケルビン数(色温度)の高いHIDやLEDバルブは、対向車や先行車のドライバーを幻惑させ、非常に危険です。
・ウインカー(方向指示器):色は「橙色(オレンジ色)」でなければなりません。また、点滅回数も1分間に60回以上120回以下と決まっています。最近流行りの「流れるウインカー(シーケンシャルウインカー)」も、基準を満たした製品でなければ違法改造となります。
・テールランプ、ブレーキランプ:色は「赤色」です。これをクリアカラーのレンズに交換し、中のバルブも見えないようにしてしまうと、後続車からブレーキをかけたことが認識されにくくなり、追突事故の原因となります。
運転席・助手席のウィンドウフィルム
プライバシーの保護やドレスアップ目的でウィンドウにフィルムを貼る方もいますが、特に運転席と助手席のガラスには注意が必要です。
運転席・助手席の側面ガラスは、フィルムを貼った状態で「可視光線透過率」が70%以上確保されている必要があります。これは、安全な視界を確保するため、そして車外から運転者の表情や動きが確認できるようにするためです。
市販されているスモークフィルムの多くは、それ自体に色がついているため、元々少しだけ着色されている純正ガラスに貼ると、透過率が70%を下回ってしまうケースがほとんどです。透過率が基準を満たさない場合、夜間や悪天候時の視界が悪化し、歩行者や自転車を見落とすなど、重大な事故につながる危険性が高まります。
エアロパーツの取り付けと車体のサイズ
車をよりスポーティーに見せるエアロパーツも、取り付け方によっては違法改造となります。
注意すべきは、車体のサイズです。取り付けたエアロパーツによって、車検証に記載されている全長、全幅、全高から一定の範囲を超えてしまう場合は、構造変更の届け出が必要になります。これを怠ると違法改造とみなされます。
また、先端が鋭利に尖っているなど、歩行者と接触した際に危険を及ぼす可能性のある形状のエアロパーツも禁止されています。
極端なローダウン(シャコタン)
車高を低くする「ローダウン」は、車をスタイリッシュに見せる定番のカスタムですが、これもやり過ぎは禁物です。
保安基準では、地面から車体の最も低い部分までの距離(最低地上高)が9cm以上確保されていなければならないと定められています。(一部例外あり)
車高が低すぎると、踏切や段差、坂道などで路面に車体の下部を擦ってしまい、マフラーや燃料タンクなどを損傷する危険性があります。また、サスペンションの可動範囲が狭くなることで乗り心地が悪化するだけでなく、本来の走行性能が発揮できなくなる可能性もあります。
違法改造車がもたらす5つの深刻なリスク
では、もし違法改造を行ってしまった場合、具体的にどのようなリスクが待ち受けているのでしょうか。「バレなければ大丈夫」という考えがいかに危険か、5つのポイントに分けて解説します。
リスク1:当然ながら車検には通らない
まず最も基本的で、多くの方が想像するリスクが「車検に通らない」ということです。
車検は、その自動車が保安基準に適合しているかどうかを定期的に検査する制度です。違法改造が施されている車は、当然この検査基準を満たせないため、車検に合格することができません。
車検が切れた車は、公道を走行することが法律で禁止されています。もし走行すれば、厳しい罰則(免許の違反点数6点、30日間の免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます。つまり、違法改造を元に戻さない限り、その車に乗り続けることはできないのです。
リスク2:警察からの整備命令と厳しい罰則
「次の車検までに元に戻せばいい」と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。違法改造は、警察による街頭での取り締まり対象となります。
もし警察官に違法改造を指摘された場合、「整備命令」という行政処分が下されます。これは、指定された期日までに違法な箇所を修理し、運輸支局で現車確認の検査を受けることを命じるものです。
この命令を無視して乗り続けると、さらに重い処分が待っています。最大で15日間の「使用停止命令」が出され、その期間は車を運転することが一切できなくなります。車のフロントガラスに使用停止を命じるステッカーが貼られてしまうため、社会的な信用も失いかねません。
さらに、悪質なケースでは、道路運送車両法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性もあります。
リスク3:【最重要】自動車保険が適用されない可能性
これが違法改造における最大のリスクと言っても過言ではありません。万が一、あなたが違法改造車で事故を起こしてしまった場合、加入しているはずの自動車保険(任意保険)が使えない可能性があるのです。
保険が使えなくなる理由は、主に二つ考えられます。
- 告知義務違反:自動車保険に加入する際、契約者は車の用途や改造の有無などを保険会社に正しく申告する義務(告知義務)があります。違法改造を行っているにもかかわらず、それを隠して契約していた場合、この告知義務違反にあたります。事故が起きた際に違法改造が発覚すると、保険会社は契約を解除し、保険金の支払いを拒否することができるのです。
- 改造と事故の因果関係:たとえ告知義務違反にならなくても、行った違法改造と事故の発生に因果関係があると判断された場合、保険金が支払われない、あるいは減額される可能性があります。例えば、基準値を超える暗いスモークフィルムを貼っていて、歩行者の発見が遅れて人身事故を起こしてしまったケースや、不正な改造マフラーの騒音が原因で救急車のサイレンに気づかず事故になったケースなどが考えられます。
もし、死亡事故などを起こしてしまい、数億円もの高額な損害賠償を命じられたとします。その時に保険が使えなければ、あなたはその後の人生の全てをかけて賠償金を支払い続けなければなりません。たった一度の軽い気持ちの改造が、人生を破滅させる引き金になり得るのです。
リスク4:事故を誘発するリスクそのものが増大する
そもそも保安基準は、自動車が安全に走るための最低限のルールです。これを無視するということは、自ら事故のリスクを高めているのと同じことです。
・制動力の低下:不正なインチアップやサスペンションの改造は、ブレーキ性能のバランスを崩し、いざという時に車がしっかり止まれなくなる危険性があります。
・視界の悪化:濃すぎるウィンドウフィルムや、対向車を幻惑させる明るすぎるヘッドライトは、自分や相手の視界を妨げ、事故の直接的な原因となります。
・被視認性の低下:テールランプの無灯火や不適切な色の使用は、後続車にあなたの車の存在や動きを正しく伝えられず、追突されるリスクを高めます。
・操作性の悪化:極端なローダウンは、車の運動性能を損ない、危険を回避するための緊急操作が難しくなります。
このように、違法改造は見た目の問題だけでなく、自動車が本来持っているはずの安全性能を著しく低下させてしまう行為なのです。
リスク5:メーカーの保証が受けられなくなる
新車や高年式の中古車には、メーカーや販売店による保証が付いています。しかし、違法改造を行った場合、この保証の対象外となることがほとんどです。
例えば、エンジンに関わる改造を行った後にエンジンが故障しても、「改造が原因の可能性がある」として保証による無償修理を断られてしまいます。その場合、高額な修理費用は全て自己負担となります。安心して車に乗り続けるために付いているはずの保証を、自ら手放してしまうことになるのです。
知らなかったでは済まされない!違法改造を防ぐために
ここまで読んで、違法改造のリスクの大きさを理解していただけたかと思います。では、どうすれば意図せず違法改造をしてしまうことを防げるのでしょうか。最後に、安心してカスタムを楽しむための具体的な方法をご紹介します。
信頼できるプロの専門店に相談する
最も確実で安心な方法は、カスタムに関する知識と経験が豊富な、信頼できる専門店に相談することです。
カー用品店やカスタムショップのスタッフは、保安基準に関する専門知識を持っています。どのようなパーツが車検に対応しているのか、どのような取り付け方をすれば合法の範囲内に収まるのかを的確にアドバイスしてくれます。自分で判断に迷う場合は、必ずプロの意見を聞くようにしましょう。安さだけで店を選ばず、実績や評判をしっかり確認することも大切です。
保安基準適合品・車検対応品を選ぶ
パーツを選ぶ際には、「保安基準適合」「車検対応」といった表示がある製品を選ぶようにしましょう。
特にマフラーなどでは、業界団体による認定プレート(例:JASMA認定品)が付いているものがあります。これらの製品は、公的機関や業界団体によって、保安基準に適合していることが証明されているため、安心して使用することができます。インターネット通販などで海外製の安価なパーツを購入する際は、日本の保安基準に適合しているかどうかが不明なケースも多いため、特に注意が必要です。
中古車を購入する際は特に注意が必要
中古車を購入する場合、前のオーナーが何らかのカスタムを施している可能性があります。一見すると格好良く見えるカスタムカーでも、実は違法改造の状態であるケースも少なくありません。
購入前には、必ず以下の点を確認しましょう。
・改造されている箇所はどこか
・その改造は保安基準に適合しているか
・車検対応品や証明書などはあるか
・必要であれば、ノーマルの状態に戻せるか
車の知識に自信がない場合は、購入する販売店のスタッフに詳しく説明を求めるか、可能であれば車に詳しい知人などに同伴してもらい、一緒にチェックしてもらうことをお勧めします。
まとめ
今回は、「違法改造」がもたらす様々なリスクについて、詳しく解説してきました。
・違法改造とは、国の定めた安全ルールである「保安基準」から外れた改造のこと。
・車検に通らないだけでなく、警察からの整備命令や罰則の対象となる。
・最も怖いリスクは、事故の際に自動車保険が適用されず、莫大な損害賠償を自己負担する可能性があること。
・違法改造は、車の安全性能を低下させ、事故のリスクそのものを高めてしまう。
・安心してカスタムを楽しむためには、信頼できる専門店に相談し、「保安基準適合品」を選ぶことが重要。
愛車を自分らしくカスタマイズすることは、カーライフの大きな楽しみの一つです。しかし、それは必ず法律というルールの上で成り立っていることを忘れてはいけません。
「知らなかった」では済まされないのが、違法改造の怖いところです。正しい知識を身につけ、ルールを守ること。それが、あなた自身と、あなたの大切な人を守り、真に豊かなカーライフを送るための第一歩となるのです。