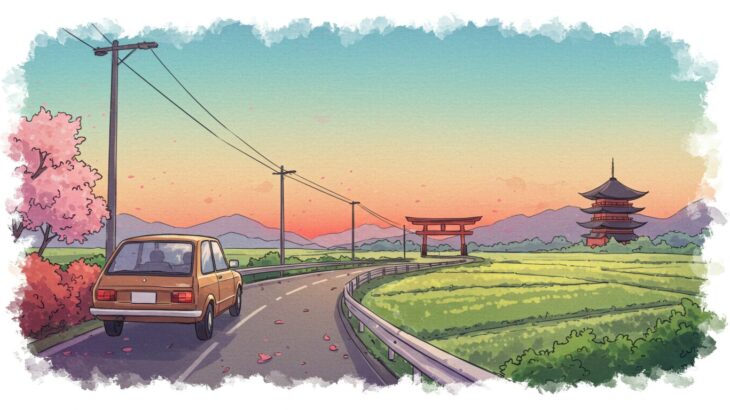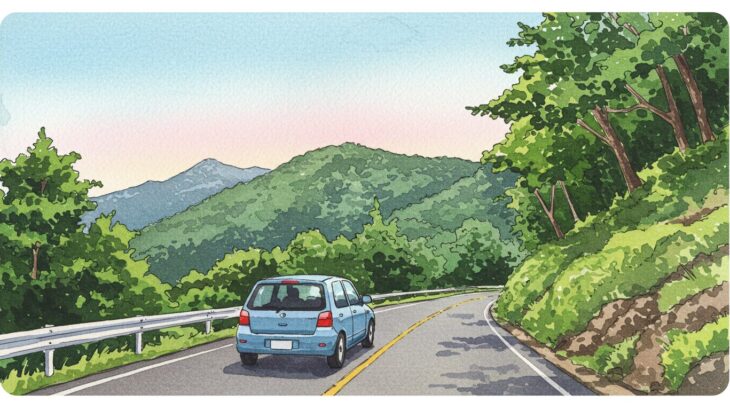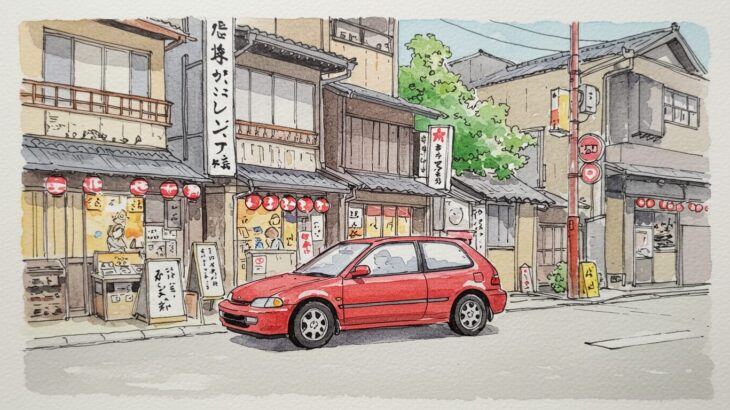運転中にヒヤリとした経験、ありませんか?免許取り立ての頃はもちろん、久しぶりの運転でドキドキしている時、つい交通ルールを忘れてしまう瞬間があるかもしれません。そんな時、万が一警察官に止められてしまったら…。「青切符」や「赤切符」という言葉は聞いたことがあっても、その違いを正確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。
「なんだかよく分からないけど、怖いもの」「罰金を払えば終わりでしょ?」そんな風に漠然と考えているとしたら、少しだけ注意が必要です。実はこの二つの切符、似ているようで全くの別物。特に「赤切符」は、あなたの今後の人生に大きな影響を与えかねない、とても重大なものなのです。
この記事では、運転初心者の方やペーパードライバーの方にも分かりやすく、「青切符」と「赤切符」の決定的な違いを、一つひとつ丁寧に解説していきます。それぞれの切符がどんな違反で渡されるのか、渡された後どうなるのか、そして何より、そんな事態にならないために私たちが日頃から何を心掛けるべきなのか。
この記事を読み終える頃には、交通違反に対する正しい知識が身につき、万が一の時にも落ち着いて対処できるようになっているはずです。そして、安全運転への意識がさらに高まり、もっと安心してハンドルを握れるようになっていることでしょう。さあ、一緒に学んでいきましょう。
交通違反の「切符」ってそもそも何?
まずは基本の確認から始めましょう。警察官が交通違反者に対して交付する書類、通称「切符」。なぜこのように呼ばれるのでしょうか。そして、なぜ交通違反は取り締まられるのでしょうか。
なぜ「切符」と呼ばれるの?
正式な名称は、後ほど詳しく解説する「交通反則告知書」や「交通事件原票」などです。これらが「切符」と呼ばれるようになった明確な由来はありませんが、細長い紙の形状が電車の切符などに似ていることから、いつしかそう呼ばれるようになったと言われています。色によってその重大さが区別されているため、「青切符」「赤切符」という通称が広く浸透しています。
交通違反を取り締まる目的
警察が交通違反を取り締まるのは、決して意地悪をしているわけではありません。その最大の目的は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることにあります。
一つひとつの交通ルールは、多くの悲しい事故の教訓から作られています。例えば、「一時停止」のルール。これは見通しの悪い交差点での出会い頭の事故を防ぐためにあります。「速度制限」は、その道路の状況で安全に停止できる速度として定められています。
ルールを破る車が1台でもいると、他の多くのドライバーや歩行者が危険に晒されてしまいます。取り締まりは、ルール違反者に対して警告を与え、社会全体の交通安全を守るための、なくてはならない活動なのです。「罰金を取るため」ではなく、「事故を未然に防ぐため」という本来の目的を理解することが、安全運転への第一歩となります。
「青切符」の正体とは?交通反則告知書を徹底解説
それでは、まず多くのドライバーにとって比較的身近な「青切符」から詳しく見ていきましょう。正式名称は「交通反則告知書」といいます。
青切符が交付される「交通反則通告制度」
青切符は、「交通反則通告制度」という仕組みに基づいて交付されます。これは、数ある交通違反の中でも、比較的軽微な違反を対象とした特別な制度です。
本来、交通ルール違反は法律違反であり、刑事事件として裁判にかけるのが原則です。しかし、毎日膨大な数の軽微な違反が発生するたびに、すべてを裁判にかけていては、警察や検察、裁判所がパンクしてしまいます。
そこで、「軽微な違反については、違反者が『反則金』を納付すれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理される」という、いわば特例措置が設けられました。これが交通反則通告制度です。
ポイントは、あくまで「行政上の手続き」で完結する、という点です。反則金を納めることで、刑事罰(前科)を科されることなく、手続きを終えることができるのです。
こんな違反が青切符の対象です(具体例)
では、具体的にどのような違反が青切符の対象となるのでしょうか。皆さんが普段の運転で遭遇しやすい、代表的な例をいくつかご紹介します。
- 速度超過(一般道で時速30km未満、高速道路で時速40km未満)
- 指定場所一時不停止等(一時停止線で止まらなかったなど)
- 駐停車違反(駐車禁止場所に車を停めたなど)
- 信号無視(赤信号や点滅信号での無視)
- 通行禁止違反(進入禁止の場所に進入したなど)
- 携帯電話使用等(運転中にスマートフォンを操作したなど)
- シートベルト装着義務違反
これらの違反は、もちろん危険な行為ですが、後述する赤切符の対象となる違反に比べると「比較的軽微」と判断され、交通反則通告制度が適用されることがほとんどです。
青切符を渡された後の流れ
万が一、青切符を渡されてしまった場合、どのような手続きが進むのでしょうか。慌てないためにも、一連の流れを把握しておきましょう。
- 現場での手続き
- 警察官から交通違反の事実を告げられ、免許証の提示を求められます。
- 警察官が「交通反則告知書(青切符)」と「反則金仮納付書」を作成します。
- 違反内容の説明を受け、告知書の「供述書欄」に署名と押印(または指印)を求められます。
- 署名・押印は拒否できる?
- ここでよくある疑問が、「署名したら違反を認めたことになるの?」という点です。その通り、署名・押印は、違反の事実を本人が認めたことを示すものとなります。
- もし、違反の事実に納得がいかない場合、署名・押印を拒否することも可能です。ただし、その場合は交通反則通告制度の適用を拒否したことになり、後日、刑事手続きに移行する可能性があります。
- 反則金の納付
- 青切符と一緒に渡される「仮納付書」を使い、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、銀行や郵便局などの金融機関で反則金を納付します。
- この期限内に納付すれば、すべての手続きは完了です。
もし反則金を支払わなかったらどうなる?
「ついうっかり納付を忘れてしまった」「納得がいかないから支払いたくない」といった理由で、期限内に反則金を納付しなかった場合はどうなるのでしょうか。
- 通告センターへの出頭と本納付
- 期限を過ぎると、後日、交通反則通告センターから「通告書」と「本納付書」が郵送されてきます。
- 本納付書には、元の反則金に加えて郵送代などの経費が上乗せされています。この本納付書を使って、指定された期限内(通告を受けた日の翌日から10日以内)に納付すれば、手続きは完了します。
- 最終的に刑事手続きへ
- この本納付の期限も過ぎてしまうと、交通反則通告制度による処理は打ち切られ、事件は警察から検察庁へ送られます(いわゆる「送検」)。
- その後、検察官が違反者を取り調べ、起訴するかどうかを判断します。起訴されれば裁判となり、裁判所が有罪か無罪か、有罪であればどのような刑罰(罰金刑など)を科すかを決定します。
- つまり、青切符の違反であっても、反則金の支払いを無視し続けると、最終的には赤切符と同じ「刑事手続き」の舞台に乗ることになるのです。軽い気持ちで放置することは絶対にやめましょう。
「赤切符」の恐怖!交通事件原票を徹底解説
次に、絶対に避けなければならない「赤切符」についてです。その正式名称は「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」、通称「交通事件原票」などと呼ばれています。その名が示す通り、これはもはや単なる行政手続きではなく、一つの「事件」として扱われることを意味します。
赤切符が交付される重大な違反とは?
赤切符は、交通反則通告制度が適用されない、悪質・危険性の高い重大な交通違反に対して交付されます。
青切符との決定的な違いは、赤切符を切られた時点で「刑事手続き」が確定する、という点です。つまり、違反者は「被疑者」という立場になり、警察の捜査を受け、検察官に送られ、裁判によって罰が決まる、という刑事事件の流れに直接乗ることになります。
反則金を納めて終わり、という簡易な手続きは存在しません。裁判で有罪判決を受ければ、それは「前科」として記録されてしまいます。
こんな違反が赤切CEPの対象です(具体例)
赤切符の対象となるのは、他人の生命や身体に重大な危険を及ぼす可能性が極めて高い、悪質な違反です。
- 酒酔い運転・酒気帯び運転
- 無免許運転
- 大幅な速度超過(一般道で時速30km以上、高速道路で時速40km以上が目安)
- 共同危険行為等(暴走族のような集団暴走行為)
- 人身事故を起こし、かつ運転者の不注意の程度が大きい場合
- 警察官の免許証提示要求や停止命令を無視するなどの悪質なケース
これらの違反は、もはや「うっかり」では済まされません。社会全体に対する重大な裏切り行為とみなされ、厳しい処分が下されることになります。
赤切符を渡された後の、厳格な手続きの流れ
赤切符を渡された後の手続きは、青切符とは比較にならないほど厳格で、精神的な負担も大きくなります。
- 警察での取り調べ
- 違反の現場で赤切符が作成された後、警察署で本格的な取り調べが行われます。違反時の状況などを詳しく聞かれ、供述調書が作成されます。
- 違反の内容によっては、その場で逮捕されるケースもあります。
- 検察庁への送致(送検)
- 警察での捜査が終わると、事件の書類や証拠品、そして被疑者の身柄が検察庁に送られます。これを「送検」といいます。
- 検察官による起訴・不起訴の判断
- 事件を送られた検察官は、被疑者を再度取り調べ、警察の捜査内容を精査し、裁判にかけるべきか(起訴)、かけないべきか(不起訴)を判断します。
- 不起訴となれば、そこで事件は終了し、前科もつきません。しかし、赤切符が切られるような悪質な違反の場合、不起訴となる可能性は低いと言わざるを得ません。
- 裁判(略式裁判または正式裁判)
- 検察官が起訴を決定すると、裁判が開かれます。
- 多くの交通違反事件では、書面審理のみで罰金額が決定される「略式裁判」という手続きが取られます。被告人が裁判所に出頭し、簡単な手続きで判決が言い渡されます。
- しかし、違反内容を否認している場合や、非常に悪質なケースでは、通常の刑事裁判と同じ「正式裁判」が開かれ、法廷で有罪か無罪かが争われることになります。
- 判決と罰則
- 裁判で有罪となれば、判決が言い渡されます。交通違反の場合、多くは「罰金刑」ですが、無免許運転や悪質な酒酔い運転、人身事故などの場合は、懲役刑や禁錮刑といった、自由を奪われる刑罰が科される可能性も十分にあります。
- そして、忘れてはならないのが、有罪判決を受けると「前科」がつく、という事実です。
赤切符と免許への影響
赤切符の対象となる違反は、違反点数も非常に高く設定されています。
- 酒酔い運転:35点
- 無免許運転:25点
- 速度超過50km/h以上:12点
- 酒気帯び運転(0.25mg/l以上):25点
免許は、過去3年間の累積点数によって、免許停止(免停)や免許取消(免取)の処分が決まります。前歴(過去の免停回数)がない人でも、6点で30日間の免停、15点で免許取消となります。
つまり、赤切符に該当する違反のほとんどは、一度犯しただけで免許停止や免許取消という、運転資格を失うほどの重い行政処分が科されるのです。
一目でわかる!青切符と赤切符の比較まとめ
ここまで解説してきた内容を、比較する形で整理してみましょう。両者の違いが明確になるはずです。
正式名称
- 青切符:交通反則告知書
- 赤切符:交通事件原票(道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式)
対象となる違反
- 青切符:一時不停止、軽微な速度超過、駐車違反など、比較的軽微な違反
- 赤切符:無免許運転、酒酔い運転、大幅な速度超過など、悪質・危険性の高い重大な違反
法的な位置づけ
- 青切符:行政処分(交通反則通告制度に基づく手続き)
- 赤切符:刑事処分(刑事訴訟法に基づく手続き)
支払うお金の種類
- 青切符:反則金(行政上の制裁金。納付すれば刑事手続きは免除)
- 赤切符:罰金(刑事罰。裁判によって金額が決定される)
その後の手続き
- 青切符:期限内に反則金を納付すれば手続き完了。
- 赤切符:警察・検察の取り調べを経て、裁判で処分が決定される。
前科の有無
- 青切符:反則金を納付すれば、前科はつかない。
- 赤切符:裁判で有罪判決(罰金刑以上)が確定すれば、前科がつく。
免許への影響
- 青切Pics:違反点数は付加されるが、1回で免許停止や取消になることは少ない。
- 赤切符:違反点数が極めて高く、1回の違反で免許停止や取消になる可能性が非常に高い。
違反しないことが一番!初心者が心に刻むべき安全運転の心得
青切符と赤切符の違いを理解すると、交通ルールを守ることの重要性が改めて身に染みるのではないでしょうか。どんなに軽い違反でも、事故につながる危険性をはらんでいます。そして重大な違反は、あなた自身の人生を大きく変えてしまいます。
最後に、切符を切られるような事態にならないために、運転初心者の方に特に心に刻んでおいてほしい安全運転の心得をいくつかご紹介します。
「かもしれない運転」を常に意識する
「だろう運転」は事故のもとです。「この交差点は車が来ないだろう」「前の車は急に止まらないだろう」。こうした思い込みが、確認を怠らせ、事故を引き起こします。
そうではなく、「もしかしたら、角から人が飛び出してくるかもしれない」「前の車が急ブレーキをかけるかもしれない」。常に最悪の事態を予測して運転することで、危険を早期に発見し、余裕をもって対処することができます。
時間と心に余裕を持った運転計画を
遅刻しそうで焦っている時、イライラしている時。そんな精神状態では、運転は必ず乱暴になります。速度を出しすぎたり、無理な追い越しをしたり、安全確認がおろそかになったり。
出かける前は、必ず時間に余裕を持った計画を立てましょう。5分、10分早く家を出るだけで、心に大きなゆとりが生まれます。そのゆとりが、安全運転に直結するのです。
自分の運転技量を過信しない
免許を取って少し運転に慣れてきた頃が、一番危険な時期かもしれません。「自分は運転がうまい」という過信が、無謀な運転につながります。
運転に「絶対」はありません。ベテランドライバーであっても、一瞬の油断で事故を起こします。常に「自分はまだ初心者だ」という謙虚な気持ちを持ち続け、基本に忠実な運転を心がけてください。
スマートフォンは運転の最大の敵
「ちょっとだけなら」「赤信号で止まっている間だけなら」。そんな軽い気持ちでスマートフォンを操作することが、どれほど危険か想像してください。視線を画面に落としたわずか2秒の間に、車は数十メートルも進みます。その先に、横断歩道を渡る子どもがいるかもしれません。
運転中のスマートフォン操作は、もはや「ながら運転」として厳罰化されています。しかし、法律で罰せられるからやらないのではなく、人の命を奪いかねない極めて危険な行為であると認識し、絶対にやめましょう。運転中は電源を切るか、ドライブモードに設定することを強くお勧めします。
まとめ
今回は、「青切符」と「赤切符」の違いについて、詳しく解説してきました。
- 青切符(交通反則告知書)は、比較的軽微な違反が対象で、反則金を納めることで手続きが完了する「行政処分」。
- 赤切符(交通事件原票)は、酒酔い運転や無免許運転などの重大な違反が対象で、裁判を経て処分が決まり、前科がつく可能性のある「刑事処分」。
この二つの違いは、天と地ほどの差があることをご理解いただけたかと思います。特に赤切符は、罰金や免許の取消だけでなく、「前科」という形であなたの社会的な信用を失墜させ、その後の人生に重い足かせをはめることになりかねません。
しかし、最も大切なことは、切符の色を気にして運転することではありません。すべての交通ルールは、あなた自身と、あなたの愛する人、そして道路を利用するすべての人々の命を守るために存在します。
今日学んだ知識を心に留め、常に思いやりと譲り合いの気持ちを持ってハンドルを握ってください。安全運転を心がけることが、結果的にあなたをあらゆる切符から遠ざけ、快適で楽しいカーライフへと導いてくれるはずです。