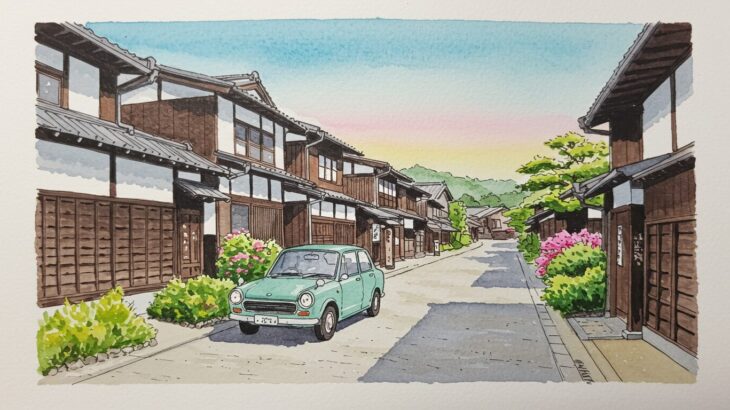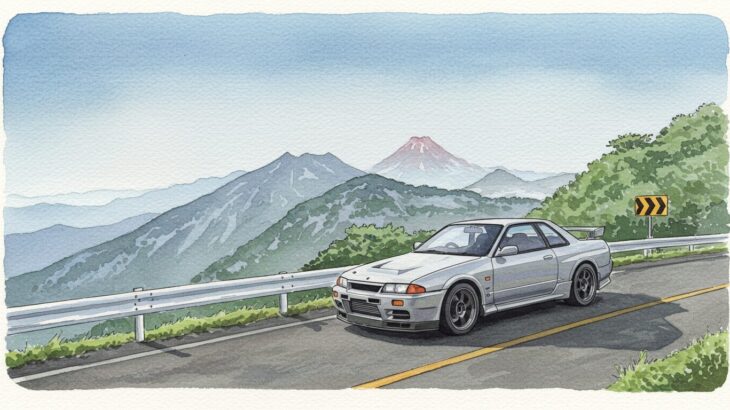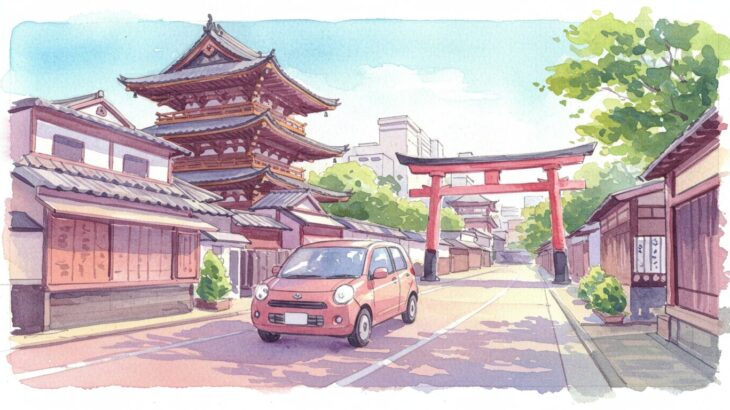「自分の車でキャンピングトレーラーを引っ張って、週末は自然の中でのんびり過ごしたいな…」
「もし友達の車が故障したら、ロープで引っ張って助けてあげられるんだろうか?」
車を運転していると、そんな場面を想像することがあるかもしれませんね。荷物を運ぶためのカーゴトレーラーや、趣味のボートを載せたトレーラーなど、街中で「けん引」している車を見かけることも少なくないでしょう。
しかし、いざ自分がやろうと思ったとき、ふと疑問が浮かびます。「あれ、けん引するのって特別な免許がいるんだっけ?」
実は、この「けん引」、ある一定の条件を満たせば、普段私たちが使っている普通免許だけで運転することが可能です。しかし、その条件を少しでも超えてしまうと、無免許運転という重い罰則の対象になってしまう可能性もある、非常に大切な知識なのです。
この記事では、運転初心者の方や、久しぶりにハンドルを握るペーパードライバーの方にも分かりやすいように、「けん引免許が必要になるケース」と「不要なケース」の境界線を、専門用語をかみ砕きながら、どこよりも丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「なるほど、そういうことだったのか!」とスッキリ理解でき、いざという時にも自信を持って対応できるようになっているはずです。安全で楽しいカーライフのために、一緒にけん引の知識を深めていきましょう。
そもそも「けん引」ってどんなこと?
まずはじめに、「けん引」という言葉の基本からおさらいしておきましょう。言葉は知っていても、その正確な意味や、なぜ免許が必要になるのかという理由までご存じの方は少ないかもしれません。
けん引の基本的な定義
けん引とは、とてもシンプルに言うと、「エンジンが付いている車(けん引車)が、エンジンが付いていない車(被けん引車)を引っ張って運ぶこと」を指します。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- キャンピングトレーラーを乗用車で引っ張る
- ボートやジェットスキーを載せたトレーラーを運ぶ
- 工事現場で使う資材を載せた台車(トレーラー)をトラックで運ぶ
- 故障して動かなくなった車を、レッカー車やロープで移動させる
このように、自分で走る力のない「被けん引車」を移動させる行為全般が「けん引」にあたります。後ろに車を連結することで、一台の車では運びきれない大きな荷物や、それ自体が居住空間になるキャンピングトレーラーなどを運ぶことが可能になるわけです。
なぜ「けん引免許」が必要になる場合があるの?
「でも、ただ車を引っ張るだけなのに、どうして特別な免許が必要になるの?」と不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。その理由は、けん引が通常の運転とは全く異なる、特別な技術と知識を必要とするからです。
想像してみてください。いつも運転している車の後ろに、もう一台分の長さと重さが加わるのです。
- 全長が長くなる:全長が倍近くになるため、交差点を曲がる時の内輪差(後輪が前輪より内側を通ること)が極端に大きくなります。いつもの感覚で曲がると、縁石に乗り上げたり、ガードレールに接触したりする危険性が高まります。
- 重量が重くなる:車全体の重さが増すため、ブレーキをかけてから完全に停止するまでの距離(制動距離)が長くなります。普段通りの車間距離では、追突事故を起こすリスクが非常に高くなります。
- バックが非常に難しい:けん引で最も難しいのがバック(後退)です。けん引車と被けん引車は連結部分で折れ曲がるため、ハンドルを切る方向と、被けん引車が曲がる方向が逆になります。例えば、トレーラーのお尻を右に振りたい場合、ハンドルは左に切らなければなりません。これは慣れないとパニックに陥りやすい操作です。
- 特殊な現象が起きやすい:急ブレーキや急ハンドルなどを行うと、けん引車と被けん引車が「く」の字に折れ曲がってしまう「ジャックナイフ現象」や、被けん引車が蛇のように左右に揺れ始めてコントロール不能になる「スネーキング現象(トレーラー・スウェイ)」といった、けん引特有の危険な現象が起こることがあります。
これらのリスクを考えれば、一定以上の大きさや重さの車をけん引する場合には、専門的な訓練を受け、その技術を証明する「けん引免許」が必要になる、というのもご納得いただけるのではないでしょうか。安全にけん引を行うためには、こうした特性を十分に理解しておくことが不可欠なのです。
けん引免許が「不要」なケースとは?
それでは、ここからが本題です。まずは、多くの方が気になるであろう「けん引免許がなくても大丈夫なケース」について見ていきましょう。実は、皆さんが想像するよりも多くのケースで、普通免許の範囲内でけん引が認められています。
条件は大きく分けて2つあります。この条件を両方とも満たしていれば、けん引免許は不要です。
条件1:引っ張られる車(被けん引車)の重さが750kg以下
最も重要なポイントが、引っ張る対象となるトレーラーや故障車などの「重さ」です。具体的には、その車の「車両総重量」が750kg以下である必要があります。
ここで、「車両総重量って何?」という疑問が浮かびますよね。簡単に言うと、「車本体の重さ(車両重量)」に、「積める荷物の最大の重さ(最大積載量)」と「乗れる人全員の重さ(乗車定員×55kg)」をすべて足した、法律上の最大の重さのことです。
- 車両総重量 = 車両重量 + 最大積載量 + (乗車定員 × 55kg)
トレーラーの場合は通常、人は乗らないので、車両重量と最大積載量を足した重さだと考えてよいでしょう。
では、750kgというと、どれくらいのトレーラーなのでしょうか。
- 小型のキャンピングトレーラー
- ジェットスキー1台を載せるためのトレーラー
- バイク1~2台を運ぶためのバイクトレーラー
- キャンプ道具などを運ぶための小型カーゴトレーラー
こうした、比較的コンパクトなトレーラーの多くは、車両総重量が750kg以下に設計されています。ご自身のトレーラーがこの条件に当てはまるかどうかは、車検証の「車両総重量」の欄を見れば一目瞭然です。必ず確認するようにしましょう。
750kg以下のトレーラーをけん引する場合、けん引する側の車(けん引車)の車検証に、「この車で〇〇kgまでのトレーラーを引っ張れますよ」という記載(950登録などと呼ばれます)を追加する手続きが必要になる場合があります。これにより、ブレーキ性能などが基準を満たしていることが証明され、安全にけん引できるようになります。
条件2:故障車をロープなどでけん引する場合
もう一つの免許不要のケースが、「故障車をけん引する」場合です。これは、車の重さに関わらず、けん引免許は必要ありません。例えば、バッテリーが上がってしまったり、エンジンがかからなくなってしまったりした友人の車を、自分の車とロープで繋いで安全な場所まで移動させる、といった緊急のケースがこれにあたります。
ただし、これはあくまで「緊急措置」であり、誰でも無条件にやっていいわけではありません。安全に行うためには、守らなければならない重要なルールがいくつもあります。
- 頑丈なロープを使う:けん引するための専用ロープを必ず使用してください。荷造り用のロープなどは絶対にNGです。
- 白い布をつける:けん引ロープの中央には、30cm四方以上の白い布を取り付けなければなりません。これは、後続車や周囲の人に「今、けん引していますよ」と知らせるための大切な目印です。
- 運転経験のある人が行う:故障車側にも、ハンドルやブレーキを操作する人が必要です。その人も、もちろん有効な運転免許を持っている必要があります。
- 合図を決めておく:運転前に、けん引する側とされる側で、発進や停止、右左折などの合図をしっかり決めておきましょう。携帯電話などで連絡を取り合いながら行うのが最も確実です。
- 急のつく操作は厳禁:「急発進」「急ブレーキ」「急ハンドル」は絶対に避けてください。ロープが切れたり、車同士が衝突したりする原因になります。ゆっくり、じんわりと操作するのが鉄則です。
- 車間距離は十分に:ロープがたるまないよう、常に適度な張りを保ちながら走行します。しかし、近づきすぎると追突の危険があるため、慎重な車間距離の維持が求められます。
- 高速道路では禁止:最も注意したいのが、高速道路(高速自動車国道や自動車専用道路)でのロープけん引は法律で禁止されているという点です。故障した場合は、ハザードランプを点灯させて路肩に停車し、速やかにロードサービスなどを呼んでください。
このように、故障車のけん引は免許不要とはいえ、非常に高い安全意識と慎重な運転が求められる行為です。安易に行うのではなく、基本的にはプロであるロードサービスに任せるのが最も安全で確実な選択肢と言えるでしょう。
けん引免許が「必要」になるのはどんなとき?
では逆に、どのような場合にけん引免許が必要になるのでしょうか。これは、先ほどご説明した「不要なケース」の条件から外れた場合、と考えると非常に分かりやすいです。
引っ張られる車(被けん引車)の重さが750kgを超える場合
これが、けん引免許が必要になる最も一般的なケースです。
引っ張るトレーラーの車両総重量が750kgを1kgでも超えた瞬間に、けん引免許が必要となります。
具体的には、以下のようなトレーラーが該当します。
- 居住設備が充実した大型のキャンピングトレーラー
- 複数のボートや大型のクルーザーを載せるためのトレーラ
- 自動車を運ぶためのキャリアカー(積載車)
- 建設機械や重量物を運ぶための大型台車
これらのトレーラーは、それ自体の重量もさることながら、荷物を積んだ際の総重量が数トンにも及ぶことがあります。これほど重いものを安全にけん引するには、やはり専門的な知識と技術が不可欠です。750kgという数字は、普通免許で安全にコントロールできる限界の重さとして設定されている、と覚えておきましょう。
複数の車をけん引する場合
あまり一般的なケースではありませんが、トレーラーを2台以上連結してけん引する場合にも、けん引免許が必要になります。日本ではあまり見かけませんが、オーストラリアの広大な大地を走る「ロードトレイン」のように、一台のトラクターが複数のトレーラーを引っ張るようなイメージです。
また、先ほどの故障車のけん引も、もし2台以上を同時にけん引するとなれば、けん引免許が必要となります。もっとも、そのような状況は現実的には考えにくく、安全性の観点からも絶対に避けるべきでしょう。
知っておきたい!けん引免許の種類と取得方法
「自分が引っ張りたいトレーラーは750kgを超えるみたいだ…」
「将来のために、けん引免許を取っておきたいな」
そう思われた方のために、けん引免許の種類や取得方法についても簡単にご紹介します。
けん引免許には3つの種類がある
実は「けん引免許」と一言で言っても、目的によっていくつかの種類に分かれています。
- けん引第一種免許これが、いわゆる一般的な「けん引免許」です。自家用のキャンピングトレーラーやボートトレーラー、仕事で使うカーゴトレーラーなど、750kgを超える車をけん引する場合に必要となります。お金をもらって荷物を運ぶ運送業の場合でも、この免許で問題ありません。
- けん引第二種免許「第二種」と付く免許は、すべて「旅客運送」、つまりお客様を乗せて運賃をいただくための免許です。トレーラーバスのように、人を乗せる被けん引車を運転する場合に必要となります。非常に特殊な免許であり、一般の方が取得する機会はほとんどないでしょう。
- 小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)これは、けん引免許の中でも限定的な免許で、「車両総重量が750kgを超え、2,000kg未満のトレーラー」をけん引する場合に取得できる免許です。一般的なけん引免許よりも教習時間が短く、費用も安く抑えられるのがメリットです。趣味で中型のキャンピングトレーラーなどをけん引したいという方に人気の免許です。
けん引免許はどうやって取るの?
けん引免許を取得するには、まず以下の条件を満たしている必要があります。
- 年齢が18歳以上であること
- 普通、準中型、中型、大型、大型特殊免許のいずれかをすでに取得していること
- 視力などの身体的な適性基準を満たしていること
取得方法は、他の運転免許と同じく、大きく分けて2つあります。
- 指定自動車教習所に通う:学科教習はほとんどなく、技能教習が中心となります。教習所で卒業検定に合格すれば、あとは運転免許試験場で適性検査を受けるだけで免許が交付されます。費用はかかりますが、最も確実で安全な方法です。
- 運転免許試験場で直接受験する(一発試験):教習所に通わず、直接試験場で技能試験を受ける方法です。費用は安く済みますが、けん引の運転は非常に特殊なため、独学での合格は極めて難しいと言われています。よほど運転に自信があり、練習する環境が整っている方以外にはおすすめできません。
これから免許取得を考えている方は、まずは指定自動車教習所に相談してみるのが良いでしょう。
免許不要でも油断は禁物!けん引時の安全運転徹底ガイド
さて、ここまでけん引免許の要不要について解説してきましたが、最もお伝えしたい大切なことはここからです。たとえ免許が不要な750kg以下のトレーラーであっても、けん引運転の難しさと危険性は変わりません。普通車を運転する感覚のままハンドルを握ると、思わぬ事故につながる可能性があります。
ここでは、免許の有無にかかわらず、けん引を行うすべてのドライバーに守ってほしい安全運転のポイントを、具体的にお伝えします。
出発前の準備と点検が何より大切
けん引運転の安全性は、走り出す前に9割が決まると言っても過言ではありません。いつも以上に念入りな準備と点検を習慣にしましょう。
- 連結部分(ヒッチメンバー)の確認:けん引車とトレーラーをつなぐ連結器が、確実につながっているかを目で見て、手で触って確認します。「ガチャン」と音がしたからOK、ではありません。ロックがしっかりかかっているか、セーフティチェーンは正しく装着されているか、複数回チェックしてください。
- 灯火類の点灯確認:トレーラー側のブレーキランプやウインカー、スモールランプなどが、けん引車と連動して正しく点灯するかを必ず確認します。これは一人では難しいので、家族や友人に協力してもらい、「ブレーキ踏んで!」「右ウインカー出して!」と声を掛け合いながらチェックするのが確実です。灯火類の不備は、後続車からの追突を招く非常に危険な状態です。
- タイヤの空気圧チェック:けん引車、被けん引車の両方のタイヤの空気圧をチェックします。特にトレーラーは長期間使わないことも多いため、空気が抜けがちです。空気圧が低いと、走行が不安定になったり、最悪の場合バースト(破裂)したりする原因になります。
- 積荷の確認:トレーラーに積む荷物は、重さが左右均等になるように配置し、走行中の振動で動かないようにロープなどでしっかりと固定してください。荷崩れは、重大事故に直結します。
これだけは押さえたい!けん引中の運転テクニック
いよいよ運転です。普段の運転とは別次元の、丁寧で繊細な操作が求められます。
- 車体の長さを常に意識する:右左折時は、とにかく「大回り」を心がけてください。運転席の感覚で交差点を曲がると、トレーラーの後輪が縁石に乗り上げたり、内側の車や歩行者を巻き込んだりする可能性があります。サイドミラーを常に確認し、「トレーラーがどこを通っているか」を把握しながら、ゆっくりと曲がる癖をつけましょう。
- 「急」のつく操作は絶対に避ける:先ほども触れましたが、「急ブレーキ」「急ハンドル」「急発進」はけん引運転における最大のタブーです。これらの操作は、ジャックナイフ現象やスネーキング現象を引き起こす最大の原因となります。すべての操作を「じんわり、ゆっくり」と行うことを徹底してください。
- 車間距離はいつもの2倍以上を確保する:車全体の重量が増えているため、ブレーキが効きにくくなっています。晴れた日でも、前の車との車間距離は普段の2倍以上、雨の日であれば3倍以上空けるくらいの気持ちで走りましょう。「ちょっと空けすぎかな?」と思うくらいが、けん引運転ではちょうど良いのです。
- バックは超高難易度と心得る:けん引時のバックは、免許を持っていても難しいものです。ハンドル操作が逆になるため、パニックになりがちです。目的地ではなるべくバックしなくても済むような駐車場所を探すのが賢明です。どうしてもバックが必要な場合は、必ず車から降りて後方の安全を確認し、可能であれば誰かに誘導してもらいながら、数センチ単位でゆっくりと動かしてください。決して無理はしないこと。広い駐車場などで、事前に練習しておくことを強くおすすめします。
- 横風に注意する:特にキャンピングトレーラーのように背が高く、側面が平らなトレーラーは、横風の影響を非常に受けやすいです。高速道路の橋の上や、トンネルの出口など、強い横風が吹く場所では、ハンドルをしっかり握り、速度を落として慎重に走行してください。
まとめ
今回は、「けん引免許」が必要なケースと不要なケースについて、詳しく解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- けん引免許の要不要を分ける大きな境界線は、引っ張られる車(被けん引車)の車両総重量が「750kg」であること。
- 750kg以下のトレーラーのけん引や、故障車を緊急で移動させるためのロープけん引は、普通免許などで行うことができる。
- 750kgを超えるトレーラーをけん引する場合は、必ず「けん引免許」が必要になる。
- 免許が不要なケースであっても、けん引運転は通常の運転とは全く違う、特別な注意と技術が求められる。
- 何よりも大切なのは、出発前の念入りな点検と、走行中の「急」のつかない丁寧な運転、そして普段の倍以上の車間距離を保つこと。
けん引ができるようになると、キャンプやマリンスポーツといった趣味の幅が大きく広がったり、いざという時に仲間を助けられたりと、カーライフがより一層豊かなものになります。
しかし、その楽しさは常に安全の土台の上に成り立っています。この記事でご紹介した知識と安全運転のポイントをしっかりと頭に入れ、ルールを守って、安全で楽しいけん引にチャレンジしてくださいね。