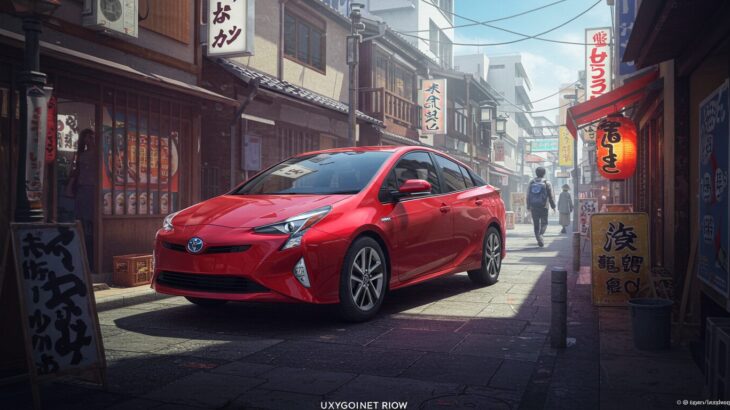「え、また法律が変わったの?」「知らないうちに違反していたらどうしよう…」
車の運転をしていると、時々耳にする道路交通法の改正。免許を取ったばかりの初心者の方や、久しぶりにハンドルを握るペーパードライバーの方にとっては、ただでさえ運転に不安があるのに、法律の変更点まで追いかけるのは大変だと感じてしまうかもしれませんね。
でも、ご安心ください。道路交通法は、私たちドライバーや歩行者を交通事故から守るための大切なルールです。改正点を正しく理解しておくことは、自分自身や大切な人を守ることに直結します。
この記事では、自動車メディアのプロのライターとして、2025年に施行される、あるいは施行が検討されている道路交通法の改正点について、どこよりも分かりやすく、丁寧にご紹介していきます。
「法律の話は難しくて苦手…」という方でもスラスラ読めるように、専門用語を極力使わず、具体的な例を交えながら解説しますので、リラックスしてお付き合いください。
この記事を読み終える頃には、新しいルールへの不安が解消され、「これなら自分でもしっかり守れそう!」と、自信を持ってハンドルを握れるようになっているはずです。
なぜ、道路交通法は頻繁に変わるの?
本題に入る前に、少しだけ「なぜ法律が改正されるのか」についてお話しさせてください。
その理由は、私たちの社会や交通環境が常に変化しているからです。
- 新しい乗り物の登場:電動キックボードのように、これまでになかった新しい乗り物が普及すれば、それに合わせた新しいルールが必要になります。
- 交通事情の変化:高齢ドライバーの増加や、スマートフォンの普及による「ながら運転」の問題など、時代と共に交通社会が抱える課題も変わってきます。
- 技術の進歩:自動運転技術が進化すれば、ドライバーの責任や義務に関するルールも見直しが必要になるでしょう。
このように、道路交通法は、私たちの安全を守るために、社会の変化に合わせて常にアップデートされ続けている「生きているルール」なのです。
それでは、ここから具体的に、ドライバーの皆さんに深く関わる改正点を見ていきましょう。
【重要】「ながら運転」の厳罰化、ついにここまで来た!
まず最初にお伝えしたいのが、「ながら運転」に関するさらなる厳罰化の動きです。
「ながら運転」とは、スマートフォンを操作しながら、カーナビの画面を注視しながらといった、運転以外のことに注意が向いてしまう危険な行為のことです。
これまでの度重なる法改正で、ながら運転の罰則はすでに厳しくなっていますが、それでも残念ながら、ながら運転が原因の悲しい事故は後を絶ちません。そこで、より一層の抑止力を持たせるため、さらに厳しい内容へと改正される可能性があります。
具体的に何がどう変わるの?(検討中の内容)
現在検討されているのは、違反点数や反則金のさらなる引き上げです。
例えば、現在でもスマートフォンを手に持って通話する「保持」だけで違反点数3点、交通の危険を生じさせた場合は違反点数6点(一発で免許停止)という厳しい罰則が科せられます。
これが、将来的には「保持」だけでも免許停止処分になる可能性や、反則金がさらに高額になることが議論されています。
また、単にスマートフォンを操作するだけでなく、ハンズフリー装置を使った通話や、カーナビ、タブレットなどの画面を2秒以上見続ける「注視」も同様に危険な行為であり、これらの行為に対する取り締まりも一層強化される見込みです。
なぜ「ながら運転」はここまで厳しくなるのか
皆さんは、時速60kmで走行している車が、わずか2秒間にどれだけ進むかご存知でしょうか?
答えは、約33.3メートルです。
25メートルプールよりも長い距離を、全く前を見ずに運転しているのと同じことなのです。もしその間に、子供が飛び出してきたり、前の車が急ブレーキをかけたりしたら…、結果は想像に難くありません。
「ちょっとくらいなら大丈夫だろう」という軽い気持ちが、取り返しのつかない事態を引き起こす。だからこそ、国は「ながら運転は絶対に許さない」という強い姿勢で、厳罰化を進めているのです。
ドライバーが今すぐできる対策
- 運転前に目的地を設定する:カーナビの操作は、必ず車が完全に停止している安全な場所で行いましょう。運転中に操作するのは絶対にやめてください。
- スマートフォンはマナーモードにして、手の届かない場所に置く:カバンの中や、後部座席など、物理的に触れない場所に置くのが最も効果的です。着信音が鳴ると、どうしても気になってしまいますよね。
- ドライブモードを活用する:スマートフォンには、運転中に通知をオフにする「ドライブモード」機能があります。これを活用するのも良い方法です。
- 同乗者に協力してもらう:誰かと一緒に乗っている場合は、電話の応対やナビの操作を同乗者にお願いしましょう。
<h2>高齢ドライバーの安全対策が変わる!免許更新の仕組み</h2>
次に、日本の交通社会が抱える大きな課題の一つである、高齢ドライバーの安全対策に関する変更点です。
年齢を重ねると、どうしても動体視力や判断力、身体機能が低下してしまうのは仕方のないことです。しかし、車がなければ生活が成り立たないという方も多くいらっしゃいます。
そこで、高齢ドライバーが安全に運転を続けられる社会を目指し、免許更新の仕組みが見直されています。
「安全運転サポートカー(サポカー)」限定免許の導入
今回の改正で注目されているのが、「安全運転サポートカー(サポカー)」に限定した免許制度の導入です。
サポカーとは、衝突被害軽減ブレーキ(いわゆる自動ブレーキ)や、ペダルの踏み間違いによる急発進抑制装置などが搭載された、先進安全技術でドライバーを補助してくれる車のことです。
運転に不安を感じる高齢ドライバーが、自らの意思でこの「サポカー限定免許」を申請・取得できるようになります。
サポカー限定免許のメリットは?
- 運転への安心感:先進安全技術が搭載された車しか運転できなくなるため、万が一のヒューマンエラーを車がカバーしてくれ、運転への心理的な負担が軽減されます。
- 免許の自主返納以外の選択肢:これまでは「運転が不安なら免許を返納する」という選択肢が主でしたが、「安全な車に乗り換えて運転を続ける」という、新しい選択肢が生まれます。
- ご家族の安心にもつながる:運転するご本人はもちろん、そのご家族の心配も和らげることができます。
ただし、注意点もあります。この限定免許でサポカー以外の車を運転した場合は、免許条件違反となりますので、十分に注意が必要です。
運転技能検査(実車試験)の導入
75歳以上で、過去3年間に一定の違反歴(信号無視や速度超過など)があるドライバーに対して、免許更新時に「運転技能検査(実車試験)」が義務付けられます。
これは、教習所のコースなどを実際に運転し、安全に運転できる能力があるかどうかを検査するものです。この検査に合格しなければ、免許を更新することはできません。
これまでの認知機能検査に加えて、実際の運転能力も確認することで、より客観的に運転継続の可否を判断する狙いがあります。
若い世代のドライバーも無関係ではない
「高齢ドライバーの話だから、自分にはまだ関係ないな」と思った方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは決して他人事ではありません。
皆さんのご両親や祖父母も、いつかはこの制度の対象になるかもしれません。その時に、ご家族としてサポカーへの乗り換えを勧めたり、運転技能検査について一緒に考えたりと、サポートしてあげることがとても大切になります。
また、サポカーに搭載されているような先進安全技術は、今や多くの新車に標準装備されています。年齢に関わらず、全てのドライバーの安全運転を支えてくれる心強い味方です。これから車を購入する、あるいは乗り換える際には、どのような安全装備がついているのかを、ぜひチェックしてみてください。
自転車の交通ルールも変わる!ドライバーが注意すべきポイント
車を運転していると、「ヒヤリ」とさせられることが多いのが、自転車の存在ではないでしょうか。交通ルールを守らない危険な自転車との接触事故も多く発生しています。
今回の法改正では、こうした状況を改善するため、自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されます。
自転車にも「交通反則切符(青切符)」が導入へ
これまでの法律では、自転車が悪質な違反をした場合、いきなり刑事罰の対象となる「交通切符(赤切符)」が交付されていました。しかし、手続きの煩雑さなどから、よほど悪質なケースでなければ適用されることは稀でした。
そこで、自動車やバイクと同じように、比較的軽微な違反に対しては反則金を納付すれば刑事罰を免れることができる「交通反則切符(青切符)」の制度が、自転車にも導入されることになりました。
対象となるのは、16歳以上の利用者で、信号無視や一時不停止、右側通行などの違反が想定されています。
なぜこれがドライバーに関係あるの?
「自転車の取り締まりが強化されるなら、ドライバーにとっては良いことじゃないか」と思われるかもしれません。もちろん、その通りです。自転車が交通ルールを守るようになれば、車との事故のリスクは確実に減るでしょう。
しかし、この改正がドライバーの皆さんに与える影響は、それだけではありません。
- 自転車側の意識向上が期待される:青切符制度の導入により、自転車も「車両」であるという意識が広まり、交通ルールを守る自転車利用者が増えることが期待されます。
- 万が一の事故の際に、過失割合が変わる可能性:これまで、自動車と自転車の事故では、交通弱者である自転車が保護される観点から、自動車側の過失が重くなる傾向がありました。しかし、今後は自転車側が信号無視などの明確なルール違反をしていた場合、その過失がより厳しく問われる可能性があります。
- ドライバーにも、より一層の安全確認が求められる:自転車側のルール遵守が期待される一方で、私たちドライバーは「自転車は急に飛び出してくるかもしれない」「ルールを守らない自転車もいるかもしれない」という危険予測運転を、これまで以上に徹底する必要があります。「自転車も青切符の対象になったから、ルールを守るはずだ」という思い込みは禁物です。
交差点での右左折時や、路地から大通りに出る際などは、スピードを十分に落とし、自転車や歩行者がいないか、これまで以上に慎重に安全確認を行う習慣をつけましょう。
まとめ:新しいルールを理解して、スマートな安全運転を
今回は、2025年にかけての道路交通法改正のポイントについて、特にドライバーの皆さんに知っておいていただきたい内容に絞って解説しました。
最後に、今日の話をもう一度振り返ってみましょう。
- ながら運転の厳罰化:スマートフォンなどの操作は、たとえ一瞬でも絶対にNG。「運転中は触らない」を徹底しましょう。
- 高齢ドライバー対策の変更:「サポカー限定免許」や「運転技能検査」が導入されます。ご家族で話し合うきっかけにしてください。
- 自転車への青切符導入:自転車側のルール遵守が期待される一方、ドライバーは「かもしれない運転」をこれまで以上に心がける必要があります。
法律の改正と聞くと、少し身構えてしまうかもしれませんが、その目的はただ一つ、「交通事故を一件でも減らすこと」です。
新しいルールを「面倒な規制」と捉えるのではなく、「自分と周りの人を守るための新しい知識」として前向きに受け止め、日々の運転に活かしていくことが、スマートで思いやりのあるドライバーへの第一歩です。
今回ご紹介した内容をしっかりと頭に入れて、これからも安全で快適なカーライフを楽しんでくださいね。