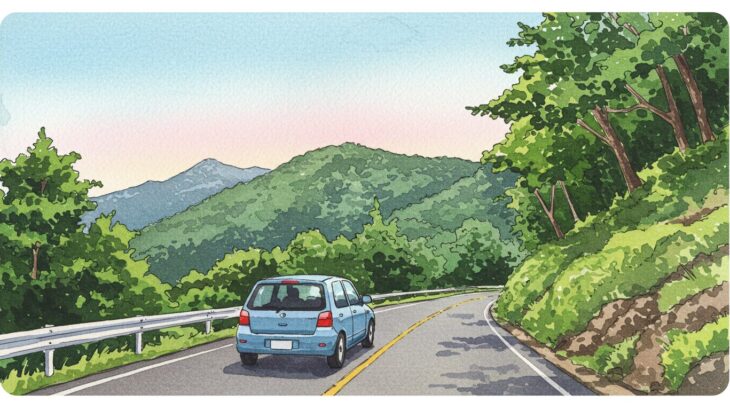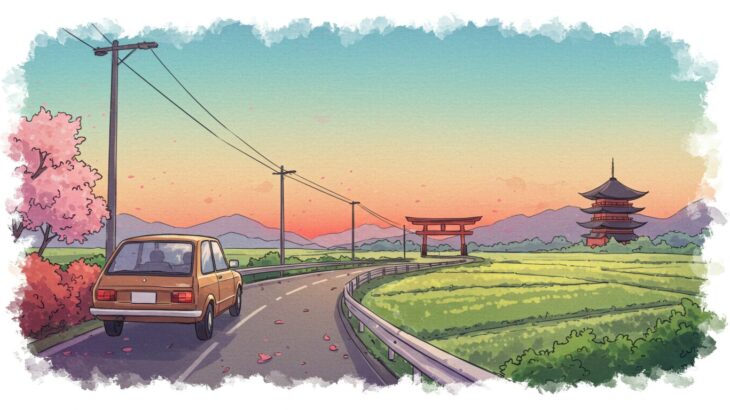「最近、スピード違反の取り締まりが厳しくなった気がする…」そう感じているドライバーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際に、持ち運び可能な「移動式オービス」の導入が進むなど、速度超過に対する取り締まりは年々進化しています。
知らず知らずのうちに速度超過をしてしまい、厳しい罰則を受けることになっては大変です。この記事では、速度超過の危険性から、最新の取り締まり方法、そして気になる罰則の詳細まで、初心者ドライバーにも分かりやすく解説します。安全運転を心がけるためにも、ぜひ最後までお読みください。
なぜ速度超過は危険なの?改めて考えるスピード違反のリスク
「少しくらいスピードを出しても大丈夫だろう」そんな軽い気持ちが、取り返しのつかない事故につながることがあります。速度超過がなぜ危険なのか、具体的な理由を見ていきましょう。
止まれる距離が長くなる(制動距離の伸長)
車はブレーキをかけてからすぐに止まれるわけではありません。運転者が危険を感じてブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めてから停止するまでの距離を「制動距離」と言います。速度が速ければ速いほど、この制動距離は長くなります。
例えば、乾いた路面で時速40kmで走行している場合の制動距離は約9メートルですが、時速60kmになると約20メートル、時速100kmでは約84メートルにも達すると言われています(タイヤや路面の状況によって変わります)。つまり、スピードを出すほど、前方の危険に気づいても間に合わずに追突したり、歩行者をはねてしまったりする可能性が高まるのです。
見える範囲が狭くなる(視野の狭窄)
運転中の視野は、車の速度が上がるにつれて狭くなっていきます。これを「視野狭窄(しやきょうさく)」と呼びます。
- 停止時: 左右約100度ずつの視野があると言われています。
- 時速40km: 視野は約65度に狭まります。
- 時速100km: 視野は約40度まで狭まってしまいます。
速度が速くなると、左右から飛び出してくる歩行者や自転車、脇道から出てくる車などを見落としやすくなり、事故の危険性が格段に高まります。
ぶつかった時の衝撃が大きくなる(衝突時の衝撃増大)
車の速度が速いほど、衝突した際の衝撃は大きくなります。これは、運動エネルギーが速度の二乗に比例するためです。
例えば、時速30kmで壁に衝突した場合の衝撃は、ビルの2階程度の高さから落下したのと同じくらいと言われています。これが時速60kmになると、ビルの5階程度の高さから落下する衝撃に相当します。速度が2倍になると、衝撃力は約4倍にもなるのです。
速度超過は、運転者自身だけでなく、同乗者や相手の車の乗員、歩行者など、多くの人を危険にさらす行為であることを忘れてはいけません。
本当に強化されている?速度超過の取り締まりの現状
「速度超過の取り締まりが強化されている」という声をよく耳にしますが、実際はどうなのでしょうか。ここでは、最近の取り締まりの傾向や、主な取り締まり方法について解説します。
取り締まり強化の背景
警察庁の発表によると、交通事故死者数は減少傾向にあるものの、依然として多くの尊い命が失われています。そして、その交通事故の原因の一つとして、速度超過が挙げられることは少なくありません。
このような背景から、より効果的な速度抑止と事故防止を目指し、警察は取り締まり方法の多様化や効率化を進めています。特に、生活道路や通学路など、歩行者の安全確保が重要視される場所での取り締まりが強化される傾向にあります。
多様化する取り締まり方法
速度超過の取り締まりには、いくつかの方法があります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。
1. 固定式オービス
特定の場所に設置されている自動速度違反取締装置です。道路の上部にカメラや赤外線ストロボなどが設置されており、速度超過した車両を自動的に撮影します。事前に「自動速度取締路線」などの警告看板が設置されていることが多いですが、見落とさないように注意が必要です。
固定式オービスには、主に以下の種類があります。
- レーダー式オービス: レーダー波を車両に照射し、その反射波から速度を測定します。
- ループコイル式オービス: 道路に埋め込まれた磁気コイルで車両を検知し、通過時間から速度を測定します。
- Hシステム(高速走行抑止システム): 高速道路などに設置されており、複数のカメラで広範囲を監視しています。
- LHシステム(ループコイル式Hシステム): ループコイル式とHシステムを組み合わせたものです。
2. 移動式オービス
近年、導入が急速に進んでいるのが「移動式オービス」です。その名の通り、場所を固定せず、三脚にカメラと速度測定器を設置して、様々な場所で取り締まりを行うことができます。
移動式オービスの主な特徴は以下の通りです。
- 神出鬼没: 従来の固定式オービスのように設置場所が限られていないため、生活道路や通学路、抜け道など、これまで取り締まりが難しかった場所でも運用可能です。
- 小型で目立ちにくい: 装置が比較的小さいため、ドライバーが気づきにくいことがあります。
- 事前警告看板がない場合も: 固定式オービスとは異なり、必ずしも事前に警告看板が設置されるとは限りません。
- レーザー式が主流: 従来のレーダー式に加え、よりピンポイントで速度を測定できるレーザー式のものが増えています。
この移動式オービスの普及により、「いつ、どこで取り締まりが行われているか分からない」という状況が生まれ、ドライバーの速度抑止効果を高めることが期待されています。
3. レーダーパトカー・白バイ
パトカーや白バイが、レーダーを使って走行中の車両の速度を測定し、違反車両を追跡して検挙する方法です。高速道路や幹線道路などでよく見られます。
パトカーの場合、違反車両の後方を一定の距離を保って追尾し、速度を測定することもあります(追尾式)。
4. ネズミ捕り(定置式速度取締)
道路脇に速度測定器(光電管式やレーダー式)を設置し、その先で警察官が待機していて、違反車両を停止させて検挙する方法です。「ネズミ捕り」という通称で知られています。
比較的短時間で場所を移動できるため、様々な場所で実施されます。
5. 覆面パトカー
一見すると一般車両と見分けがつかないパトカーです。主に交通量の多い道路や高速道路で、周囲の車の流れに紛れて走行し、速度超過や車間距離不保持などの違反車両を取り締まります。
追い越し車線を猛スピードで走行する車や、不自然な運転をしている車がターゲットにされやすいと言われています。
最近の取り締まりの傾向
- 移動式オービスの積極的な活用: 前述の通り、移動式オービスの導入が全国的に進んでおり、これまで手薄だった生活道路やゾーン30(最高速度30km/hの区域)などでの取り締まりが増えています。
- 「点」から「線」への取り締まり: 特定の地点だけでなく、一定の区間全体での速度抑制を目指す動きも見られます。例えば、区間内に複数の移動式オービスを時間差で設置したり、パトカーが巡回を強化したりするケースです。
- 悪質・危険な違反への重点的な取り締まり: 大幅な速度超過や、飲酒運転、あおり運転などと複合した危険な速度違反に対しては、より厳しい姿勢で臨む傾向があります。
これらの傾向からも分かるように、速度超過に対する取り締まりは、よりきめ細かく、そして予測しにくい形へと変化しています。常に法定速度・制限速度を守る意識を持つことが、これまで以上に重要になっています。
知っておかないと怖い!速度超過の罰則の詳細
速度超過で取り締まられた場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。ここでは、反則金、違反点数、そして場合によっては刑事罰に至るケースまで、詳しく見ていきましょう。罰則は、違反した場所(一般道か高速道路か)と、超過した速度によって細かく定められています。
罰則の基本:反則金と違反点数
多くの速度超過は、「交通反則通告制度」の対象となります。これは、比較的軽微な交通違反について、一定期間内に「反則金」を納付すれば、刑事手続(裁判)に進むことなく事件が処理されるという制度です。
同時に、違反の種類と程度に応じて「違反点数」が付されます。この違反点数が一定の基準に達すると、免許停止や免許取消といった行政処分を受けることになります。
一般道路における速度超過の反則金と違反点数
| 超過速度 | 違反点数 | 反則金(普通車) |
| 15km/h未満 | 1点 | 9,000円 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1点 | 12,000円 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2点 | 15,000円 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 3点 | 18,000円 |
| 30km/h以上50km/h未満 | 6点 | 簡易裁判で罰金 |
| 50km/h以上 | 12点 | 簡易裁判で罰金 |
※注意点:
- 上記の表は普通車の場合です。大型車や二輪車など車種によって反則金額は異なります。
- 30km/h以上の速度超過(一般道)は、交通反則通告制度の対象外となり、刑事手続(通常は略式裁判による罰金刑)が取られます。この場合、「反則金」ではなく「罰金」が科されます。罰金額は裁判官が決定しますが、一般的に6万円~10万円程度になることが多いようです。
- 「6点」または「12点」が付されると、前歴がない場合でも一発で免許停止処分となります。
高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)における速度超過の反則金と違反点数
| 超過速度 | 違反点数 | 反則金(普通車) |
| 15km/h未満 | 1点 | 9,000円 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1点 | 12,000円 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2点 | 15,000円 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 3点 | 18,000円 |
| 30km/h以上35km/h未満 | 3点 | 25,000円 |
| 35km/h以上40km/h未満 | 3点 | 35,000円 |
| 40km/h以上50km/h未満 | 6点 | 簡易裁判で罰金 |
| 50km/h以上 | 12点 | 簡易裁判で罰金 |
※注意点:
- 上記の表は普通車の場合です。
- 40km/h以上の速度超過(高速道路)は、交通反則通告制度の対象外となり、刑事手続(罰金刑)が取られます。罰金額は一般的に8万円~10万円程度になることが多いようです。
- 「6点」または「12点」が付されると、前歴がない場合でも一発で免許停止処分となります。
「罰金」と「反則金」の違い
よく混同されがちな「罰金」と「反則金」ですが、法的な意味合いが異なります。
- 反則金: 交通反則通告制度に基づき、行政処分として納付するお金です。納付すれば刑事責任は問われません。前科はつきません。
- 罰金: 刑事罰の一種で、裁判所から支払いを命じられるお金です。納付しても前科がつきます。
一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の大幅な速度超過をすると、反則金の範囲を超え、刑事罰である罰金が科される可能性が高くなります。この場合、赤切符(告知票)が交付され、後日、検察庁からの呼び出しがあり、簡易裁判所で罰金額が決定される流れが一般的です。
免許停止・免許取消となるケース(行政処分)
違反点数が一定の基準に達すると、運転免許の効力が一時的に停止されたり(免許停止)、取り消されたり(免許取消)する行政処分を受けます。処分の内容は、過去3年間の免許停止処分の前歴回数と、累積された違反点数によって決まります。
免許停止処分の基準(前歴なしの場合)
| 違反点数 | 免停期間 |
| 6~8点 | 30日間 |
| 9~11点 | 60日間 |
| 12~14点 | 90日間 |
例えば、一般道で30km/h以上40km/h未満の速度超過をした場合、違反点数は6点なので、前歴がなければ30日間の免許停止処分となります。
免許取消処分の基準(前歴なしの場合)
| 違反点数 | 欠格期間 |
| 15~24点 | 1年間 |
| 25~34点 | 2年間 |
| 35~39点 | 3年間 |
| 40~44点 | 4年間 |
| 45点以上 | 5年間 |
「欠格期間」とは、免許を再取得できない期間のことです。免許取消になると、この欠格期間が経過しないと、運転免許試験を再び受けることができません。
例えば、一般道で50km/h以上の速度超過をした場合、違反点数は12点です。これだけでは前歴なしの場合、90日間の免許停止ですが、もし他に違反があり合計で15点以上になると免許取消の対象となります。また、酒酔い運転(35点)やひき逃げ(35点)など、極めて悪質な違反の場合は、一発で免許取消となることもあります。
前歴がある場合の注意点
過去に免許停止処分を受けたことがある場合(前歴がある場合)、より少ない違反点数で、より重い処分(長い免停期間や免許取消)を受けることになります。
例えば、前歴1回の場合、
- 4~5点で60日間の免停
- 6~7点で90日間の免停
- 8~9点で120日間の免停
- 10点で免許取消(欠格期間1年)
となります。前歴が多いほど、処分は厳しくなりますので、過去に処分歴がある方は特に注意が必要です。
刑事罰(懲役刑・罰金刑)となるケース
前述の通り、大幅な速度超過(一般道30km/h以上、高速道40km/h以上)の場合は、交通反則通告制度の対象外となり、刑事罰の対象となります。多くは略式裁判による罰金刑ですが、非常に悪質な場合や、事故を起こして人を死傷させた場合などは、正式な裁判となり、懲役刑が科される可能性もあります。
例えば、危険運転致死傷罪(アルコールや薬物の影響、制御困難な高速度、ことさらに信号無視などによる死傷事故)が適用された場合、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役(最高で20年)と、非常に重い罰則が科されます。
速度超過を防ぐ!安全運転のための7つのポイント
うっかり速度超過をしてしまい、後悔することのないように、日頃から安全運転を心がけることが大切です。ここでは、速度超過を防ぐための具体的な運転のポイントを7つご紹介します。
1. 法定速度・制限速度を必ず確認する
運転する道路の法定速度や制限速度を常に意識しましょう。
- 法定速度: 標識や標示で最高速度が指定されていない場合の最高速度です。一般道では通常60km/h(原付は30km/h)、高速道路では通常100km/h(対面通行区間や一部区間を除く)です。
- 制限速度: 道路標識や道路標示によって指定されている最高速度です。場所によって細かく設定されているため、見落とさないように注意が必要です。特に、住宅街や学校の近くなど、歩行者が多い場所では低い速度に設定されていることが多いです。
「この道はいつも空いているから」「前の車もスピードを出しているから」といった自己判断は禁物です。必ず標識を確認し、指示された速度を守りましょう。
2. 速度計をこまめに確認する習慣をつける
運転に慣れてくると、つい速度計を見る回数が減ってしまいがちです。しかし、体感速度は実際の速度とずれることがあります。特に、長時間の運転や、下り坂、追い風の状況などでは、無意識のうちに速度が上がりやすいものです。
- 発進時、加速時
- 巡航時も定期的に
- 下り坂に差し掛かる前
- 標識で制限速度が変わった直後
など、意識して速度計を確認する癖をつけましょう。
3. 周囲の車の流れに惑わされない
「周りの車が速いから、自分も合わせないと危険だ」と感じることがあるかもしれません。しかし、周囲の車が速度超過をしているからといって、それに合わせる必要はありません。むしろ、それが集団での速度超過を助長し、危険な状況を生み出すことにつながります。
自分のペースを守り、法定速度・制限速度を遵守することが最も安全です。もし後続車からプレッシャーを感じるようであれば、安全な場所で道を譲るなどの対応を考えましょう。
4. 時間と心に余裕を持った運転計画を立てる
時間に追われていると、どうしても焦りが生まれ、速度を出しがちになります。出発前に目的地までのルートや所要時間を確認し、余裕を持った運転計画を立てましょう。
- 出発時間を早めに設定する
- 渋滞情報などを事前に確認する
- 休憩時間を考慮に入れる
特に初めて行く場所や、慣れない道を運転する際は、時間に余裕を持つことが精神的な安定につながり、安全運転を促します。
5. 最新の交通情報を確認する習慣を
カーナビゲーションシステムやスマートフォンの地図アプリ、ラジオの交通情報などを活用し、最新の交通状況を把握することも大切です。
- 渋滞情報: 渋滞を避けることで、焦りを減らし、無理な運転を防ぎます。
- 事故情報: 事故発生区間を避ける、または慎重に運転することができます。
- 天候情報: 雨や雪、霧などの悪天候時は、視界が悪くなったり、路面が滑りやすくなったりするため、通常よりも速度を落として慎重に運転する必要があります。
6. 運転支援技術を正しく活用する(過信は禁物)
最近の車には、運転をサポートしてくれる様々な先進技術が搭載されています。
- クルーズコントロール: 設定した速度を維持してくれる機能です。高速道路などでの単調な運転時に、速度を一定に保つのに役立ちます。
- アダプティブクルーズコントロール(ACC): 前方の車との車間距離を保ちながら追従走行してくれる機能です。
- 速度標識認識機能: カメラで道路標識を読み取り、メーター内やヘッドアップディスプレイに表示してくれる機能です。うっかり制限速度を見落とすのを防ぐのに役立ちます。
これらの技術は便利ですが、あくまでも運転の補助です。システムを過信せず、常に周囲の状況に注意を払い、危険を感じたらすぐに自分で操作できるようにしておくことが重要です。
7. 体調管理と適度な休憩を
疲労や睡眠不足は、集中力や判断力を低下させ、安全運転に大きな影響を与えます。運転前日は十分な睡眠をとり、体調が優れないときは運転を控える勇気も必要です。
長距離運転の場合は、2時間に1回程度は休憩を取り、軽いストレッチをするなどしてリフレッシュしましょう。眠気を感じたら、無理せず仮眠を取ることが大切です。
もし速度超過で取り締まられたら…その後の流れと対処法
万が一、速度超過で取り締まられてしまった場合、どのような手続きが進められるのでしょうか。慌てずに対応するためにも、基本的な流れを理解しておきましょう。
1. 違反の告知と切符の交付
警察官に停止を求められ、速度超過の事実を告げられます。その後、違反の種類や程度に応じて、以下のいずれかの切符(告知票)が交付されます。
- 青切符(交通反則告知書): 交通反則通告制度が適用される比較的軽微な違反(一般道で30km/h未満、高速道で40km/h未満の速度超過など)の場合に交付されます。反則金の仮納付書が一緒になっています。
- 赤切符(告知票・運転免許証保管証): 交通反則通告制度の対象外となる重大な違反(一般道で30km/h以上、高速道で40km/h以上の速度超過、酒気帯び運転など)の場合に交付されます。この場合、刑事手続が進められます。運転免許証は一時的に預かられ、代わりに「運転免許証保管証」が交付されることがあります(無免許運転になるわけではありません)。
2. 反則金の納付(青切符の場合)
青切符を交付された場合は、記載された期限内に反則金を金融機関(銀行や郵便局)で納付します。期限内に納付すれば、刑事手続に進むことなく事件は処理され、前科もつきません。
もし期限内に納付しなかった場合は、通告センターから本納付書が郵送されてきます。それでも納付しないと、刑事手続に移行し、検察庁から呼び出しを受ける可能性があります。
3. 刑事手続(赤切符の場合)
赤切符を交付された場合は、後日、検察庁から出頭要請があります。検察官による取り調べを受け、多くの場合、略式裁判による罰金刑が求刑されます。
略式裁判に同意すると、裁判所から罰金の納付命令が出され、指定された金額を納付することになります。罰金を納付すると前科がつきます。
もし、略式裁判に同意しない場合や、検察官が正式裁判が相当と判断した場合は、公開の法廷で裁判が行われることになります。
4. 違反点数の累積と行政処分
反則金の納付や罰金の支払いとは別に、違反点数が累積されます。累積点数が一定の基準に達すると、公安委員会から免許停止や免許取消の行政処分に関する通知が届きます。
- 意見の聴取・聴聞: 免許停止処分(90日以上)や免許取消処分に該当する場合、処分が決定される前に、本人に意見を述べる機会(意見の聴取または聴聞)が設けられます。ここで、違反の状況や反省の情、今後の安全運転への誓いなどを述べることができますが、処分が軽減されるとは限りません。
- 処分の執行: 処分が決定されると、出頭して免許証を返納し、免停期間が開始されたり、免許が取り消されたりします。
- 違反者講習・停止処分者講習: 免許停止期間を短縮できる制度として、違反者講習(累積点数が6点で30日免停の場合など)や停止処分者講習があります。受講は任意ですが、講習の成績によって免停期間が短縮されることがあります。
5. 不服申し立てについて
警察官の取り締まりや、行政処分に対して不服がある場合は、不服申し立ての制度があります。しかし、その手続きは専門的な知識を要する場合が多く、認められるケースも限られています。不服申し立てを検討する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:安全運転はドライバーの責任。速度を守り、事故のないカーライフを
今回は、車の速度超過の取り締まりと罰則について詳しく解説しました。移動式オービスの普及などにより、速度超過の取り締まりはよりきめ細かくなっています。しかし、取り締まりがあるから速度を守るのではなく、自分自身や大切な人の命、そして他の道路利用者の安全を守るために、常に法定速度・制限速度を遵守することが何よりも重要です。
速度超過は、制動距離を伸ばし、視野を狭め、衝突時の衝撃を増大させる非常に危険な行為です。一瞬の油断や気の緩みが、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。
この記事で解説した罰則の重さからも、速度超過がいかに社会的に許されない行為であるかがお分かりいただけたかと思います。反則金や罰金だけでなく、免許停止や免許取消といった行政処分、さらには前科がつく刑事罰に至るケースもあるのです。
安全運転は、車を運転するすべての人の責任です。
- 常に速度計を確認する
- 時間と心に余裕を持つ
- 法定速度・制限速度を必ず守る
これらの基本的なことを守り、思いやりのある運転を心がけることで、悲しい交通事故は必ず減らせます。今日から改めて、安全運転の意識を高め、快適で安全なカーライフを送りましょう。