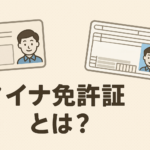自動車を所有していると必ずかかってくるのが自動車税です。「自動車税(種別割)」と「軽自動車税(種別割)」という名称は耳にしたことがあっても、具体的にどれだけの税金がかかるのか、あるいはどんな条件で税額が変わるのかまでしっかり把握している方は意外と少ないかもしれません。さらに、新車購入時や一定年数が経過した車への特別な優遇税制や重課税なども存在し、複雑だと感じる方も多いでしょう。
この記事では、普通自動車(登録車)と軽自動車の自動車税(種別割)について、それぞれの基本的な税額や排気量別の目安、環境性能による優遇や経過年数による重課などを整理してわかりやすく解説します。車にかかるコストを正しく理解し、負担額をシミュレーションしておくことは、車の維持管理や買い替えの検討にとっても重要です。
自動車税(種別割)とは
自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点の自動車(普通自動車・小型自動車)所有者が、都道府県に対して納める地方税のことです。車の用途や総排気量などを基準として税額が決められており、いわゆる“排気量が大きい車ほど税額が上がる”仕組みになっています。
一方、軽自動車の所有者は「自動車税(種別割)」ではなく、市区町村に対して「軽自動車税(種別割)」を納めます。ただし、課税主体(都道府県か市区町村か)の違いはあるものの、基本的にはどちらも同じような仕組みで、総排気量(軽自動車の場合は排気量区分ではなく“軽自動車”としての区分)や車種区分によって税額が定められています。
自動車税(種別割)は原則として、4月1日時点で所有している人がその年度(4月1日~翌年3月31日)の税金を支払うことになります。「4月2日に車を購入した場合は?」という疑問もあるかもしれませんが、その年度の税金を支払う義務はありません。ただし、4月2日以降に購入して、翌年の4月1日時点で所有している場合は、翌年度分の自動車税(種別割)が課税されます。
また、総排気量は「車検証」の「総排気量又は定格出力」の欄を見れば確認できます。1,000cc、1,500cc、2,000cc…といった単位で分類されることが多いので、車選びの際はここをチェックすると税額の目安を把握しやすいでしょう。
自家用乗用車の自動車税(種別割)区分
自家用乗用車(登録車)は、2019年10月1日以降に初回新規登録した車の場合、下記のように排気量ごとに税額が定められています。通常、年式が新しいほど税額は下記にある標準額が適用されます(ただし、後述する「重課」の対象になると別の税率が適用されます)。
▼自家用乗用車(登録車)における自動車税(種別割)の目安(2019年10月1日以降初回新規登録の車)
- 1,000cc以下:25,000円
- 1,000cc超~1,500cc以下:30,500円
- 1,500cc超~2,000cc以下:36,000円
- 2,000cc超~2,500cc以下:43,500円
- 2,500cc超~3,000cc以下:50,000円
- 3,000cc超~3,500cc以下:57,000円
- 3,500cc超~4,000cc以下:65,500円
- 4,000cc超~4,500cc以下:75,500円
- 4,500cc超~6,000cc以下:87,000円
- 6,000cc超:110,000円
排気量が大きくなるにつれて税額が上がっていくのは、燃料消費量や環境負荷が大きくなりがちだからという背景があります。一方で、環境性能に優れた車の場合は減税措置が設けられており、一定期間は税負担を軽くできる制度も用意されています。
軽自動車税(種別割)とは
排気量が660cc以下の軽自動車については、市区町村へ「軽自動車税(種別割)」を納めます。2015年4月1日以降に初回新規検査を受けた軽自動車の場合、自家用乗用車であれば年額10,800円が目安です。軽自動車は総排気量ではなく“軽自動車規格”として区分されるため、普通自動車と違って細かい排気量別の段階はありません。
軽自動車は経費が安く済むことから、維持費を抑えたい方には魅力的な選択肢と言えるでしょう。そもそも自動車税(種別割)の高さがネックになって、普通車の購入を敬遠する人もいます。その点で、軽自動車税(種別割)の安さは非常に大きなメリットです。
軽自動車税(種別割)の基本額
軽自動車税(種別割)については、以下の金額が適用されます(2015年4月1日以後に初回新規検査を受けた自家用乗用車の場合)。
- 年間税額:10,800円
この10,800円というのは、あくまで“基本”の金額であり、後述の「重課」や「グリーン化特例(軽課)」が適用されると変動します。軽自動車だからといって常に10,800円だけで済むわけではなく、車の年式や燃費性能によっては重課・軽課の対象になる可能性がある点には注意が必要です。
グリーン化特例(軽課)の概要
排出ガス性能や燃費性能が優れた「エコカー」に対しては、環境負荷の小さい車の普及を促すために「グリーン化特例」と呼ばれる軽減措置が適用される場合があります。一定の条件を満たす電気自動車やハイブリッドカー、天然ガス自動車などは、翌年度の自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)が軽減される仕組みです。
グリーン化特例の適用期間と対象
2023年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車が対象になります。燃費基準や排出ガス性能の基準を満たす必要があり、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(一定の排出ガス規制をクリアしているもの)などが該当します。
たとえば、電気自動車や燃料電池自動車などは、次年度の自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が「概ね75%軽減」となるなど、大きな優遇を受けられます。適用を受けるためには、初回新規登録(あるいは届出)の時点で適合していることが条件なので、購入を検討している方は対象となるモデルかどうかをよく確認するとよいでしょう。
経過年数による「重課」の仕組み
グリーン化特例によって税額が軽くなる制度がある一方、年式の古い自動車については環境性能が相対的に低いとみなされ、税率が重くなる「重課」の制度もあります。これは環境負荷を抑える目的で、新しい車への買い替えを促す狙いがあるとされています。
乗用車(普通車・登録車)の重課
ガソリン車やLPG車(液化石油ガス車)で、新車新規登録から13年を超えた車、ディーゼル車は新車新規登録から11年を超えた車については、概ね15%重課されます。ただし、電気自動車や燃料電池自動車など環境性能に優れた車両はこの重課の対象外です。トラックやバスなどは、乗用車よりも重課率が異なる場合があります。
具体例として、総排気量1,000cc以下のガソリン車であれば標準税額は25,000円ですが、13年超経過している場合は概ね15%上乗せされます。15%上乗せされた場合、28,750円程度になるイメージです(実際には円単位で調整される場合があるため、お住まいの自治体の情報をご確認ください)。
軽自動車の重課
軽自動車(自家用乗用車)の場合、初めて車両番号の指定を受けてから13年が経過すると、もともとの税額10,800円よりも概ね20%重課されます。20%重課となると、1万2千円台後半前後に上がる可能性があります(実際の計算では端数処理が行われる場合があります)。
したがって、軽自動車であっても古い年式の車を所有している場合は、思ったより税額が高くなることがありますので注意が必要です。特に中古車を購入する際には、その車が初度登録(届出)されてから何年経過しているかを必ず確認するようにしましょう。
排気量別:普通車(登録車)の自動車税(種別割)具体例
実際に、総排気量別で自動車税(種別割)の負担額がいくらかかるのか確認してみましょう。上記の一覧を改めてまとめると次のとおりです。なお、2019年10月1日以後に新車新規登録された場合の基本的な年額です。
- 1,000cc以下:25,000円
- 1,000cc超~1,500cc以下:30,500円
- 1,500cc超~2,000cc以下:36,000円
- 2,000cc超~2,500cc以下:43,500円
- 2,500cc超~3,000cc以下:50,000円
- 3,000cc超~3,500cc以下:57,000円
- 3,500cc超~4,000cc以下:65,500円
- 4,000cc超~4,500cc以下:75,500円
- 4,500cc超~6,000cc以下:87,000円
- 6,000cc超:110,000円
同じ車種でも排気量の違うグレードが設定されていることがあります。購入時だけでなく、維持費として毎年支払いが発生するため、エンジンの大きさ選びは家計管理やライフスタイルを左右する重要なポイントになるでしょう。また、標準税額のほかに、「重課」や「軽課」の適用の有無によって実際の納税額は変わりますので、合わせて注意してください。
自動車税(種別割)と関連するその他の税金
車を所有していると、以下のような税金も関連してきます。自動車税(種別割)だけでなく、車検費用や購入時のコストも含めてトータルの維持費をしっかり把握することが大切です。
自動車重量税
車検時に納める国税で、車両重量に応じて税額が変わります。基本的に車検ごと(新車時は3年、以降は2年ごと)に課税されるため、年度ごとの支払いとはタイミングが異なります。自動車重量税もエコカー減税の対象となる場合があり、条件を満たすと税額が軽減されるケースがあります。
消費税(購入時)
新車や中古車の購入時には、車両価格に消費税がかかります。消費税は購入時に一度だけですが、車両価格が高額になればその分大きな負担となります。さらにカーナビやオプション品にも同様に消費税がかかる点に注意が必要です。
自動車取得税(廃止済)と環境性能割
かつては自動車取得税が存在しましたが、これは消費税率10%への引き上げに伴い廃止され、「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、排気ガスや燃費性能などが優れた車であればあるほど低税率になる仕組みで、購入のタイミングにおいて負担額が左右されるのが特徴です。ただし、これは2021年10月以降、名称や内容が大きく変化するなど複雑化している部分もあり、購入時には販売店などで最新情報を確認するのがベストです。
自動車税(種別割)の納付方法とスケジュール
自動車税(種別割)は一般的に4月1日時点の所有者を対象として、その年の5月頃に納付書が郵送されます。納税期限は通常5月末となるため、忘れずに支払うようにしましょう。もし5月中旬を過ぎても納付書が届かない場合は、管轄の都道府県税事務所などに問い合わせるとスムーズです。
納付方法
近年は納付書を持ってコンビニや金融機関で支払うだけでなく、クレジットカードやネットバンキングでの支払いにも対応している地域が増えています。また、PayPayなどのスマホ決済が使える場合もあります。自分のライフスタイルに合わせて便利な方法を選択するとよいでしょう。
自動車税を滞納するとどうなる?
もしも自動車税(種別割)を期限内に支払わなかった場合、延滞金が発生し、さらに長期間放置すると車検を受けられないなどの不利益を被ることがあります。最悪の場合、財産の差押えといった強制徴収が行われる可能性もありますから、必ず期日までに納付を済ませるように心がけましょう。
車を選ぶときに気を付けたいポイント
自動車税(種別割)は年に1回の負担ですが、車の維持費を考えるうえでは非常に重要な項目です。特に排気量が大きい車を検討している場合は税額が跳ね上がりやすいので、購入前に十分シミュレーションしておくと安心です。また、年式の古い中古車を安く手に入れたつもりでも、重課が適用されると毎年の税負担が大きくなることがあります。
近年は環境性能の高いモデルが増えており、グリーン化特例などで翌年度の自動車税が軽減される可能性もあるため、総合的に判断することが大切です。燃費性能が良ければガソリン代も抑えられるので、結果的に維持費をトータルで減らせるかもしれません。
初度登録年月・経過年数の確認は必須
特に中古車を購入する際は「初度登録年月」をチェックし、その車の経過年数を把握しましょう。車検証を見れば、初度登録年月が記載されています。購入予定の車が、すでに重課の対象期間に入っていないか、あと何年で重課の対象になりそうかを確認するだけで、大きな差額を避けることができます。
グリーン化特例が適用されるかのチェックも重要
電気自動車やハイブリッドカーなどは購入時の価格が高い傾向にありますが、グリーン化特例による軽課の適用で翌年度の税負担をかなり抑えられるケースがあります。ガソリン代も含めたランニングコストを考えれば、長い目で見て負担が少なくなる可能性もあるため、購入時には税制面のメリットをしっかりと比較検討することをおすすめします。
まとめ
これから車を購入する方は、事前に自動車税(種別割)の負担額をシミュレーションしておくことが大切です。排気量別の基本税額だけでなく、対象車に適用されるグリーン化特例(軽課)や重課の可能性なども含めて総合的に検討してください。環境性能に優れた車を選ぶことで、維持費を抑えつつ快適なカーライフを実現できるかもしれません。
ぜひこの記事の情報を参考に、税金面からも賢く車を選んでみてください。