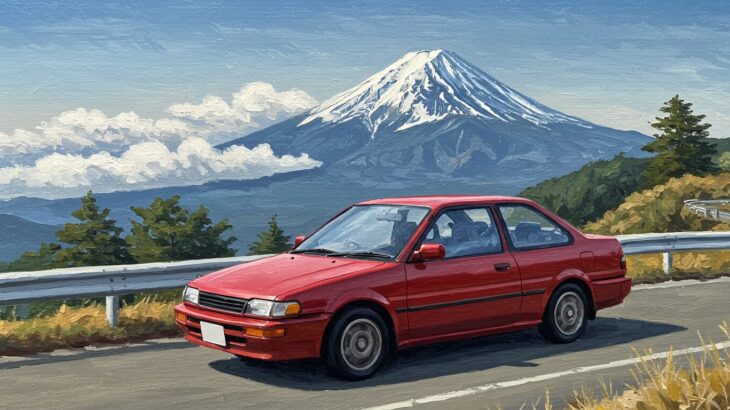この記事では、レンタカーを利用中に事故に遭った場合の対応や保険の仕組み、補償範囲・自己負担リスク、慰謝料の請求先などを詳しく解説します。初めてレンタカーを借りる方はもちろん、旅行や出張などで日頃からレンタカーを利用する方にも役立つ情報を網羅しています。万一のトラブルを回避し、安心してレンタカーを利用できるように、しっかりと内容を把握しておきましょう。
レンタカー事故は保険で補償されているの?
レンタカーで起こりうる交通事故にはさまざまなケースがあります。小さな接触事故から大きな人身事故まで、そのリスクは自家用車と同様に存在しているのです。しかし、レンタカーの場合はほとんどの事業者が自動車保険に加入しているため、通常は一定の補償が受けられます。ここでは、レンタカー利用時に適用される保険や、自分の保険を併用できるケースについて解説します。
レンタカー会社が加入している保険について
レンタカー事業者は、法律で定められているとおり自動車保険に加入する義務があります。これにより、利用者が車を借りている最中に事故を起こした場合でも、以下のような保険が適用される可能性が高いです。
- 対人賠償保険
事故の相手方が死傷した場合に、相手の治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料などを補償します。多くの場合は無制限の契約が主流ですが、事業者によっては限度額が設定されているケースもあるので注意が必要です。 - 対物賠償保険
相手方の車両や建物、ガードレールなどの物的損害を補償するための保険です。こちらも多くのレンタカー会社では対物賠償が無制限になっていますが、契約内容を確認しておくと安心です。 - 車両保険
借りたレンタカー自体が事故で損壊した場合の修理費用などを補償します。ただし、免責金額が設けられている場合が多く、修理費用の一部を自己負担しなければならないケースがあります。 - 人身傷害保険
レンタカーに乗っていた人(運転者や同乗者)が死傷した際、治療費や休業損害、慰謝料などを補償する保険です。通常の自動車保険に付帯されているケースが多いですが、契約内容によっては適用範囲が制限されていることもあります。
このように、レンタカー会社は複数の保険制度を整えています。しかし、保険によっては一定の免責金額が設定されている場合や、補償の上限がある場合もあるため、借りる前に補償内容を把握しておくことが大切です。
自分の保険が利用できる場合
レンタカー事故であっても、状況によっては自分が加入している自動車保険を利用できることがあります。その代表例が「他車運転特約」です。他車運転特約に加入している場合、他人名義の車やレンタカーを運転している際に起こした事故でも、自分の保険を使って補償を受けることができます。
なお、他車運転特約の適用にはさまざまな条件があるため、加入している保険の証券や約款を事前に確認しておきましょう。特に、家族限定など運転者の範囲に制限をかけている保険の場合、「レンタカーが適用外」となるケースもあるため要注意です。
レンタカー保険で補償されないケースとは?
レンタカー会社の保険に加入していれば安心…と考える方は少なくありませんが、実際には保険適用外となるケースも存在します。契約内容や事故の態様によっては自費で負担しなければならない可能性があるため、どのようなケースが補償対象から外れるのかを把握しておきましょう。
レンタカー保険が適用されない事故例
以下のような事情がある場合、レンタカー会社の保険が適用されない可能性が高く、損害を全額自己負担することになります。
- 契約者本人以外が勝手に運転した場合
レンタカー契約上の運転者が限定されているにもかかわらず、勝手に第三者が運転して事故を起こすと、保険適用外となるリスクがあります。 - 無免許運転や飲酒運転
当然ながら法律違反の運転形態で起こした事故は保険が適用されません。レンタカーだからといってそのような危険運転が許されるはずはなく、加害者は重い責任を負うことになります。 - 返却期限超過中の事故
正規の契約期間を過ぎているにもかかわらず、そのまま車を使用し続けて事故を起こすと、保険では補償されない場合があります。 - 警察やレンタカー会社への届出を怠った場合
事故が起こったにもかかわらず、警察に通報しなかったり、レンタカー会社への連絡をせずに自己判断で示談してしまうと、保険適用が拒否されることがあります。 - 貸渡約款に違反する行為
レンタカーを運転中に、契約上禁止されている行為(競技への参加、危険物の運搬など)をしていた場合にも、保険金の支払いを受けられない可能性があります。
免責金額の存在
レンタカー保険には、たいてい「免責金額」が設定されています。これは、事故が起きても保険会社が補償しない金額のことで、修理費用などの一定額を利用者が自己負担する仕組みです。たとえば、免責5万円の車両保険で修理費用が50万円かかった場合、45万円は保険で賄われる一方、残りの5万円は自己負担となります。
また、免責金額の支払い義務を免除するために「免責補償制度(CDW)」というオプションが用意されていることも多いです。通常は1日あたり1000~2000円程度の追加料金を支払う必要がありますが、心配な方はCDWをつけておくことで、万一のときの自己負担をなくせる可能性があります。
保険の補償限度額を超える損害
レンタカー会社によっては、対人・対物の保険が無制限で付帯されている場合が多いものの、中には上限が設定されているケースも存在します。もし補償限度額を超える規模の事故を起こしてしまうと、超過分を利用者自身で負担する必要が出てきます。
大きな人身事故や高額な賠償が絡む事故では、医療費や休業損害、相手車両の高級車の修理費などが莫大な金額になる可能性があります。こういった状況に備え、レンタカーを借りる前には契約書や約款をしっかり確認し、必要に応じて追加オプションや自分の保険を併用するとよいでしょう。
ノンオペレーションチャージ(NOC)
レンタカーを事故で破損させてしまい、修理が必要になると、その間レンタカー会社は車を貸し出せなくなります。これは営業損害として「ノンオペレーションチャージ(NOC)」の支払いを請求される場合があります。NOCはレンタカー会社の損失を補填するもので、一般的には2~5万円程度が相場です。多くの場合、レンタカー保険ではこのNOCはカバーされず、利用者の自己負担となる点に注意が必要です。
加害者に請求できる賠償項目
もし自分がレンタカーを利用中に被害を受けた場合には、加害者(または加害者側の保険会社)に対して損害賠償を請求できます。ここでは、交通事故で請求できる主な賠償項目を整理しましょう。
積極損害
積極損害とは、被害者が実際に支払った費用など、事故によって直接的に発生した出費のことを指します。具体的には以下のようなものがあります。
- 治療費
病院への入院・通院費、医療器具や薬剤費など、怪我の治療に必要と認められる費用がすべて含まれます。 - 付添看護費
怪我の程度によっては、医師の指示のもと、付添看護が必要とされる場合があります。職業付添人を雇った場合はその実費、近親者が付添いをした場合でも一定額が認められる場合があります。 - 入院雑費
入院生活で必要となる日用品、洗濯代、テレビカードなどの雑費にあたる出費は、1日あたり定額で計上されることが多いです。 - 通院交通費
通院にかかった電車やバスなどの公共交通機関の運賃、自家用車を利用した場合のガソリン代なども損害に含まれます。
消極損害
消極損害とは、事故に遭わなければ得られたであろう収入や利益が、事故のために失われてしまったことを指します。代表的には以下の項目があります。
- 休業損害
会社員や自営業者が怪我の治療で仕事を休むことで収入が減少した分だけでなく、家事従事者(専業主婦・主夫)が家事をできなかったことによる損害も含まれます。 - 逸失利益
後遺障害が残って労働能力が低下し、将来にわたって得られるはずだった収入が減少する場合に請求できるのが後遺障害逸失利益です。万が一、事故で被害者が死亡してしまった場合には、死亡逸失利益として、生存していれば得られたはずの将来の収入分を加害者に請求できます。
慰謝料
慰謝料は、事故による精神的苦痛に対する賠償金です。大きく3つの種類に分かれます。
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
怪我による入院・通院期間を基準に算定され、治療期間が長引くほど慰謝料の金額も増加します。 - 後遺障害慰謝料
後遺障害が残った場合、その程度(等級)によって金額が定められています。 - 死亡慰謝料
被害者が死亡した事故の場合、被害者本人の精神的苦痛だけでなく、遺族の慰謝料も考慮して算定されます。
レンタカー事故の慰謝料請求先
レンタカーでの事故とひと口にいっても、被害者側・加害者側いずれかがレンタカーを運転していたかによって請求相手が変わる場合があります。
被害者がレンタカーを運転していた場合
被害者自身がレンタカーを運転していて事故に巻き込まれた場合、基本的には加害者本人が保険に加入している(任意保険を含む)ことが多いので、加害者の保険会社に対して損害賠償を請求します。加害者が任意保険に入っていない場合でも、少なくとも自賠責保険(強制保険)から一定の補償を受けることが可能です。
なお、自分にもある程度の過失があった場合(いわゆる過失相殺)には、加害者から全額を補償してもらうことはできません。とはいえ、レンタカー会社の保険(人身傷害保険など)が適用されるケースもあり、自身の負担を軽減できる可能性があります。
加害者がレンタカーを運転していた場合
事故の加害者がレンタカーを利用していた場合、賠償責任を負うのは加害者本人だけでなく、レンタカー会社も「運行供用者」として賠償義務を負うことがあります。これは自動車損害賠償保障法(自賠法)の規定によるもので、レンタカー会社が車を運行させる利益を得ていることから、被害者保護の観点でその責任を問われるという考え方です。
ただし、実際の交渉では、加害者が加入している保険会社やレンタカー会社の保険会社が代理で対応することが一般的です。複数の保険会社が絡むこともあり、示談交渉が複雑化する場合もあるため、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
レンタカーで事故に遭ったらすべきこと
レンタカー事故に限らず、交通事故が起きた場合には適切な初動対応が肝心です。レンタカーの利用中であれば、通常の事故対応に加えて、レンタカー会社への連絡なども欠かせません。以下の手順を把握しておきましょう。
身の回りの安全を確保し、負傷者がいる場合は救護活動
まずは二次被害を防ぐために車を安全な位置に移動し、周囲の安全を確保します。負傷者がいる場合は救急車を呼ぶ、けが人を安全な場所に移動させるなど、道路交通法で定められた救護義務をしっかりと履行しましょう。
警察に通報
事故の当事者は必ず警察に通報し、事故証明書の発行を受ける必要があります。これを怠ると、保険を利用した補償が受けられなくなるおそれがあります。軽微な事故でも「大したことないから」と放置せず、必ず110番で警察を呼びましょう。
レンタカー会社へ連絡
レンタカー利用中の事故の場合、レンタカー会社への連絡は貸渡約款で定められている必須事項です。連絡を怠った場合、レンタカー会社の保険を利用できなくなる可能性もあります。警察への届出を行ったら、すぐにレンタカー会社に状況を報告し、指示を受けてください。
事故状況の確認・記録、相手の連絡先の把握
事故直後は気が動転してしまいがちですが、後日過失割合などで揉めるリスクに備え、事故現場の状況を写真や動画で残しておくのが非常に重要です。車両の損傷部位や道路環境など、事故を客観的に示す証拠を確保しておきましょう。また、加害者・被害者双方の連絡先や加入保険などの情報交換も忘れずに行ってください。
病院を受診し、けがの治療
自覚症状が軽い場合でも、事故後は必ず医療機関で診察を受けることが大切です。時間が経ってから痛みが出てくるケースも少なくありませんし、警察や保険会社への手続きの際に必要となる診断書も取得できます。事故との因果関係を争われるリスクを減らすためにも、できるだけ早期に受診しましょう。
保険会社との示談前に弁護士へ相談
怪我が完治または症状固定した段階で、保険会社から示談金(賠償額)の提示が行われることが多いです。しかし、保険会社から提示される金額は、裁判で認められる基準(弁護士基準)に比べて低額であるケースもあります。提示額に納得できない、あるいは金額妥当性を知りたい場合には、示談書にサインする前に弁護士へ相談するのが望ましいです。
弁護士に依頼すれば、面倒な示談交渉を任せられるうえ、弁護士基準に基づいた妥当な金額を主張することができます。また、弁護士費用特約がついていれば、費用面の負担も大きく減らせるため、早期に相談しておくと安心です。
まとめ
レンタカーは便利で気軽に利用できる反面、万が一事故が起きた場合には、自家用車とは違うルールや補償範囲、自己負担リスクを把握しておかないと、思いもよらないトラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、レンタカー会社の保険には免責金額や補償限度額が設定されている場合があるため、契約前の確認が重要です。また、ノンオペレーションチャージ(NOC)の存在も見落としがちなので注意しましょう。
事故後の対応としては、まずは安全確保と警察への連絡が最優先です。次にレンタカー会社への報告を行い、事故証明書の取得や現場の証拠保全、必要な治療を早めに進めることが肝心です。示談の話が出たら、早い段階で弁護士や専門家に相談することをおすすめします。そうすることで、保険会社からの提示額が適正かどうか判断でき、正当な賠償金を得る可能性を高められるでしょう。
不安な点がある場合は、遠慮せずに弁護士や消費生活センターなどに問い合わせをしてみてください。事前の知識があれば、事故の際にも冷静な判断がしやすくなります。レンタカーを利用する機会がある方は、ぜひこうした知識を頭に入れて、万一のトラブルに備えておきましょう。